初夢の調べ
すみません、もうすぐバレンタインデーなのに、今頃になって初夢の話?と思われた方もいらっしゃるでしょう。
でも、そうなんです、その初夢のお話なんです。
多分、初夢というのは、元日に寝た後に見る夢のことなのだと思いますが、だとすると、とっても奇妙なものでした。
いつもと違って、とっても断片的な夢でしたが、こんなものが登場したのでした。
自分で経営しているかのような、なかなかいいレストラン。その居心地のよい場所を後にし、向かった先の山では、一生懸命に植林をしている。一本、一本、丁寧に。まるで、神の手がマッチ棒大の木々を大地に植え込んでいるかのように。そして、それが終わると、森の奥にでも潜んでいるのか、爆弾犯の捜索に取りかかる。
場面は一転し、目覚める頃には、ラフマニノフの「ピアノ協奏曲第2番(ハ短調Op.18)」が耳元に流れ、目の前には、やたら音符の多い楽譜が広がる。
まあ、「植林」や「爆弾犯」なんかの夢の分析はさておいて、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番は、彼のピアノ協奏曲の中でも、一番好きなものです。
あの情熱的な旋律の盛り上がり、そして、あふれ出る感情。ほんとに、名曲です。
この曲は、人気テレビドラマ『のだめ カンタービレ』でもお馴染みですよね。千秋先輩が、ストレーゼマンの指揮の下、見事に弾き上げた協奏曲。
個人的には、ちょっとテンポが遅いようにも感じましたが、それでも、舞台の演技はなかなかのものでした。
協奏曲、交響曲、ピアノの小品、合唱曲と、数あるラフマニノフの作品の中でも、一番有名な、彼らしい名曲ですね。
ドラマの中でも言われていましたが、このピアノ協奏曲には、こんなエピソードがあるそうです。
若手作曲家としてもピアニストとしても、自信満々の青年ラフマニノフ。ところが、彼が第1交響曲を世に発表すると、途端に手のひらを返したように酷評にさらされる。
それに耐え切れず、強度の神経衰弱に陥ったラフマニノフを救ったのが、精神科医のニコライ・ダール医師。
4ヶ月に渡る暗示療法の末、めでたく立ち直ったラフマニノフ青年は、イタリア旅行から戻って、さっそく協奏曲を書き始めた。
そんな暗闇から脱した状態で生まれたのが、この2番。だからこそ、あれほどの感情がほとばしっているのでしょうね。
わたしが初夢で聴いたのは、情熱ほとばしる部分じゃなくって、第2楽章アダージョ・ソステヌート(Adagio sostenuto)。
華やかな第1楽章と第3楽章の間にはさまれ、穏やかな、美しい旋律で、皆がふっと息をつくところ。
これを聴きながら目覚めたわたしは、平和な気分に満ちていたのでした。
音って不思議です。まわりの環境や、自分の心の中が、如実に反映される。
それは作り手にしても、弾き手にしても言えることだと思います。
テレビでオペラを観たんです。モーツァルトの「魔笛(Magic Flute)」を英語の台本にして、舞台芸術もミュージカルみたいに斬新にしたもの。ニューヨークのメトロポリタンオペラの公演です。
たった2時間オペラを聴いていただけなのに、そのあとピアノを弾いてみると、音がまったく違っている。深くて、リッチ。それに、あでやか。言いたいことが言えている、そんな感じかもしれません。
体の調子が悪くてめまいがするとか、練習不足で指が動かないとか、そんなことは関係ないくらいに、まったく音質が違うんです。
自分では気が付いていないけれど、オペラから、何かを吸い取ったのでしょうか。
音楽を勉強するのにヨーロッパがいいって、よく言いますよね。「のだめちゃん」のドラマでもそうでした。それって、こういうことなのかもしれませんね。
知らないうちに、頭からだけじゃなくって、肌からも栄養を吸い取っている。街角で聞く騒音も、いつも通る何気ない石造りの風景も、みんな栄養になっている、そういうことなのではないでしょうか。
わたしはよく、作曲家と同じ国を生まれ故郷とする演奏家を選びます。世代はまったく違うけれど、ごちゃごちゃと説明されることもなく、作曲家を表現できているんじゃないかと思って。
そういう人を聴いていると、「こんな音作りは、日本人じゃ絶対にやらないよね」って思うことがあります。楽譜に並ぶ音符の間に、何か特別なものが見えているみたい。
その場所の空気を吸って、水を飲んで、何かしら自然と吸収するものがある。
あ、なんだかつい暴走してしまいましたが、何であんな初夢見たんだろうって、不思議に思っているんです。
それは、大好きな曲ではあるけれど、どうして第1楽章でも第3楽章でもなく、静かな第2楽章なんだろうって。
今年は、この路線で、穏やかに行きなさいってことなのかな。
音楽のこぼれ話:これを書くにあたって、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を聴き返しておりました。
勿論、いつ聴いても名曲ではあるのですが、第1楽章を半分過ぎる頃、自然と涙が湧いて来るのです。そして、「そうかい、そうかい、わかったよ」と、27歳の青年ラフマニノフに語りかけておりました。
時に炎(ほむら)跳び、時に水が流れる。どんな形にせよ、苦しみを一度でも経験したことのある人には、よくわかる曲なのかもしれません。
わたしが2番を聴いたヴラディーミル・アシュケナージの演奏も、作曲家と同胞の名士として深く心を打つものでした。
が、実は、ラフマニノフ自身も、凄い演奏家なのです。はっきり申し上げて、ピアニストとしてのラフマニノフも、曲作りに劣らず、天才と言うべきでしょう。
それは、『Rachmaninoff Plays Rachmaninoff(ラフマニノフがラフマニノフを弾く)』というCDで、片鱗を感じ取ることができます。
ピアニスト・ラフマニノフに関しては、アメリカのヘンダーソンという批評家が、こう記したそうです。
ラフマニノフがこの世に在る時に生を享け、演奏を聴くことができて、その運命の星のめぐり合わせに、ただただ感謝するしかないと。
わたしも、雑音の入った録音ではなく、実際にその場で聴いてみたかったと、残念に思うばかりです。
手元にあるCDでは、ラフマニノフ自身がピアノ協奏曲1番と4番、そして、「パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43」を弾いています。
「パガニーニ」の方は、なんと、1934年のボルティモアでの初演のひと月後に、レオポルド・ストコフスキー指揮、フィラデルフィア管弦楽団という、同じ顔ぶれで録音されたものです。
ラフマニノフが61歳の時の演奏ですが、まあ、よく指が動くこと!彼の技巧は、現代にしても、決して引けを取りません。
そして、ご自身が弾くと、やっぱり、きらびやか。ストコフスキーの指揮ということもあるのかもしれませんが、次から次へと繰り広げられる変奏は、まったく飽きさせることがありません。
ラフマニノフの演奏を見事に踏襲しているアシュケナージもそうですが、なんだってロシア人って、あんなに指が動くんでしょう?しかも、みなさん、一様にロマンティスト。
1934年、ラフマニノフがスイスのルツェルン湖畔で書いたという「パガニーニ」は、初演された当時、あまり評判が良くなかったそうです。聴衆への演奏効果だけをあてにしている曲だと。
けれども、誰でも一度は聴いたことのある、あの美しい「第18変奏アンダンテ・カンタービレ(Andante cantabile)」を耳にすると、そんな批判なんて、どこかに吹っ飛ぶのではないかと思うのです。
おっと、ついラフマニノフを語ってしまいましたが、もし気が向かれたら、も一度聴いてみてくださいね。
ちなみに、冒頭の写真は、書家の母の手作りカードでした。新年のあいさつにふさわしい和紙を見つけたようで、ちょっと遊んでみたようです。

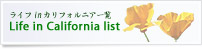
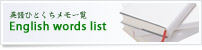
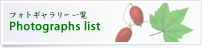

 Page Top
Page Top