宮若市〜福岡の離れの宿
<エッセイ その224>

6月のある夕刻、いつもと違った夕焼けの光景が目に飛び込んできました。
空には厚く雨雲がかかっているのに、向こうの外海は、晴れ。
能古島(のこのしま)に落ちる夕陽は、外洋を照らし出し、グレーとオレンジのタピストリーを織りなしている。
こちらは、博多湾に浮かぶ島々と太陽がつくったアート作品。
右は志賀島(しかのしま)、左に浮かぶのは手前が能古島、奥が玄海島(げんかいじま)。陸続きの志賀島は福岡市東区、船で行く能古島と玄海島は西区に属します。
博多湾を臨む、福岡市の夕焼け。刻々と移り行く自然のアートのワンショットなのでした。
近頃は、海や山に近いし、海産物や農作物も美味しい都会ということで、福岡市の人気は上昇中のようです。
もうひとつの魅力は、県内外に行きやすいという、フットワークの軽さもあるでしょうか。
高速道路や幹線道路、交通機関が整備されていて、郊外に行くのもずいぶんと楽になっています。
そんな福岡市の郊外に、宮若市(みやわかし)があります。
今までは高速道路で通り過ぎる街だったのですが、「福岡の離れの宿」というキャッチフレーズにつられて、5月下旬、一泊旅行で行ってみたのでした。

宮若市は、福岡市から北東へ、北九州市に向かうちょうど真ん中にあります。
福岡市内から九州自動車道に乗り、北九州方面へ向かうと、二つ目の「若宮IC」で降ります。ここまでおよそ30分の短い旅。
「若宮 宮若(わかみや みやわか)」という、まるで回文のような看板が印象的です。
宿に行くには早いので、近くにある花菖蒲(はなしょうぶ)の名所に寄ってみました。休耕田を手入れして、小さな花菖蒲園にした花畑。
が、今年は開花が遅れて、たった一輪しか咲いていませんでした!
こちらは、小さいながらも花菖蒲の名所として知られていて、満開ともなると、さぞかし美しいことでしょう。
ボランティアの方でしょうか、緑色に繁る元気な葉っぱの向こうには、女性が何人か花の世話をしていらっしゃるのが見えました。

この辺りは、静かな住宅街。レンガ造りの塀に、懐かしさを覚えます。わたしが入学した小学校も、レンガ造りの塀で囲まれていましたが、近年、地震対策なのか壊されたのが残念です。
宮若市といえば、もともとは炭鉱の街だったとか。
幕末に近くの直方(のうがた、現・直方市)で生まれた貝島太助(かいじまたすけ)が、40を過ぎて炭鉱を興し、貝島炭鉱として名を馳せるようになりました。
ここ宮若では、露天掘りの方式が採られ、複数の露天坑が80ヘクタールほどに広がっていたとか。今は、露天坑も埋められ、当時の面影は残りません。
わたし自身は、「貝島」という名を聞くと、若干のもの寂しさを覚えるのです。
ピーク時には、1万人の作業員が働き、家族を含めると3万人ほどを抱えたという貝島炭鉱。福利厚生に重きを置く貝島太助は、私立の学校を創設して、子供たちの教育にも尽力します。
ところが、炭鉱の暮らしは決して楽ではありません。ですから、「学校に来て、学びなさい」と奨励しても、子供たちは来てくれません。なぜなら、ボタ山で石炭を拾って、家計を助けたいから。
大正期に国際条例で女性の炭鉱労働が禁止されるまで、一家のお母さんも炭鉱に入り、石炭の運び出しに従事します。子供もボタ拾いをするのは、当たり前の時代。そこで、太助は、学校に来た子にはお金をあげてまで、子供たちに教育を広めようと尽力したそう。自身は、学校に行きたくても行けなかった、という思いもあったようです。
そんな貝島家の家訓は、ひとつのことに集中して極めよ、ということ。それが祟って、全国的に炭鉱の不振が続く中、昭和51年(1976年)には閉山を迎えました。
以前、このお話を直方の石炭記念館で伺ったとき、貝島家の地域への貢献を知ったとともに、炭鉱だけではなく他の産業にも参入していたら、さぞかし成功されていたのだろうと、もの寂しさを覚えたことでした。
宮若市や直方市に行くと、どことなく懐かしさを感じるのです。それは、日本の産業の源に、石炭や鉱石といった資源があり、産業全体が炭鉱や鉱山で働く方々に支えられていたからなのでしょうか。
と、いきなりお話が大きくそれてしまいました!
そう、福岡市の郊外・宮若への一泊旅行のお話です。
「福岡の離れの宿」というキャッチフレーズにつられてやって来たのは、古民家風に建てられた温泉宿。
6室すべてが、かけ流し温泉付きの離れになっています。
お宿全体は、しっとりと歴史を感じますが、4年前にオープンしたばかり。

古民家風の部屋に入ると、天井の梁は、大分県由布院(ゆふいん)から運ばれた、立派な部材。その他は、古民家を模して造られた、落ち着いた佇(たたず)まいです。
お風呂の窓には、ガラスではなく、スライド式の板がはめ込まれています。わずかに開けられた隙間からは、風は入るけれど、虫は入らない、という昔の知恵が光ります。
かけ流しの湯は、24時間流しっぱなし。レモン湯にして、お客様をおもてなしです。
この筑豊から大分にかけては、水が豊かなことで有名なのでしょう。お湯の成分はわかりませんが、髪を洗ったらサラサラになったような気もします。
宿泊した5月26日は、奇しくも「源泉かけ流し温泉の日」。前日まで知らなかったのですが、まさに記念日にふさわしい、贅沢なかけ流しのお風呂でした。
お宿では、嬉しい対応もありました。
部屋に入ると、ベッドルームの上にあるカーテンのない天窓が気になったのですが、すぐに外から「すだれ」を二重にかけていただくことで対処していただきました。
東向きの窓で、朝日がまぶしくて目覚めることを心配したのですが、昔ながらのすだれは、思いのほか効果的でした。
そして、天窓の下の四角い窓には、連れ合いがパティオの長椅子のクッションをはめ込んでみたら、ピシャリと合うのです! 厚地のクッションは、遮光と防音を兼ね備えた安心感がありました。
子供の頃、仲間を集めてキャンプに行ったら、鍋を忘れたことに気がついて、マンホールの蓋を活用して海岸でジンギスカンを楽しんだという連れ合い。クッションを窓にはめ込むとは、まだまだ、ひらめきは冴えています。

このお宿を選んだ理由は、夕食にもありました。
敷地内ではフレンチレストランと懐石料理のレストランが営業していて、晩ご飯はどちらかを選択するようになっています。この晩は、フレンチを選びました。
福岡市内でレストランを経営していたシェフは、宮若で地産地消のお店を開きたいと、こちらへ引っ越して来られたそう。
宮若では、フレンチレストランで使われる野菜はすべて栽培されているようで、地元から仕入れた新鮮な食材が使われます。
近くでは宗像(むなかた)の鐘崎(かねざき)漁港をはじめとして、海産物も豊富ですし、宮若で育てられた宮若牛など地元産のお肉もあります。

レストランの裏庭では、ハーブやエディブルフラワー(食べられる花)がたくさん育てられていて、食べ頃になったら、みんなで採って涼しいワインセラーで保存されるそう。
ワインセラーの棚には、瓶詰めにされた野菜やハーブもたくさん並べられていて、珍しい自家製ピクルスは、お料理の味をさらに深めてくれています。
まさに、南フランスで修行されたシェフの本領発揮です。瓶詰めや摘んだばかりのハーブいっぱいのワインセラーは、日本のレストランではあまり見かけない光景でした。
見ても食べても美味しいコース料理。残念ながら、ひとつひとつ何だったか覚えていないのですが、野菜中心でさまざまな香りたっぷりのお料理は、お腹にもやさしいのが嬉しかったです。

一泊したあとは、宮若を少しだけ観光しました。
山に囲まれた盆地にある宮若市。もともとお宿のまわりには、田畑が広がり、遠くで農作業をされている様子も見えます。これだけで、絵になるような風景です。
春は、一面にピンク色のレンゲが咲き、秋は、畦道に沿って赤い彼岸花が咲き誇る。
山から流れ落ちる清流では、この時期、ホタルも飛んでいるのでしょう。
水も豊富で、土壌も豊か。農産物を作れば、コンクールでも賞を獲得するほどの折り紙つきだそう。ですから、地産地消のレストランを、と思われるシェフもいらっしゃるんですね。
そして、この若宮盆地でもうひとつ有名なものといえば、雲海だそうです。
雨の翌日、湿気の残る早朝、こちらの高台からは、若宮盆地を雲海が覆い、雲海から頭を出す山々が墨絵のように見えることがあるとか。
ここは、黒丸地区にある清水寺(せいすいじ)というお寺。標高200メートルの高台にあり、盆地を見渡すには絶好の場所です。

清水寺は、奈良時代の最盛期・天平(てんぴょう)年間に行基(ぎょうき)が開いたと伝わるお寺。
行基といえば、仏教を広めようと全国行脚の旅に出て、治水や道路整備などの社会事業でも知られる僧侶。のちに聖武天皇の命により、奈良・東大寺の大仏造立に奔走した高僧としても知られます。
そんな行基さんが開いたお寺なので、古刹の多いこの鞍手(くらて)地方でも最古の寺といわれます。ご本尊の千手観音菩薩像は、行基作とも伝わるそう。
小さな境内には、本堂や鐘楼、近代に建てられた五重塔、青々と繁る藤棚と、時代を超えた造形物が並びます。
中でも、こちらの野舞台(のぶたい)は、印象的でした。野舞台とは、神楽や獅子舞を行う常設舞台のこと。この地域では、宮永天満宮や乙野(おとの)天満宮にも見られます。
神仏がいらっしゃる正面に建てられ、本来は奉納を目的としていますが、踊りや芝居にも使われ、見物人も境内に集まって一緒に楽しみました。
残念ながら、豪雨の影響でしょうか、こちらの野舞台は改修が必要な状態ですが、民間伝承の芸能が大切にされてきた歴史を感じます。
きっと、この静かな集落にも、神楽に通じる、小粋な趣味人もいらっしゃることでしょう。
普段は、この清水寺を訪れる人も少なく、高台からの景色も独り占めです。が、桜や紅葉の時期と、竹灯籠まつりの年末年始は、境内も大いに賑わうようです。
山門を下っていくと、左右には水田が広がります。
田植えしたばかりのみずみずしい若緑が美しく、印象的でした。
空は青く、清々しい。山々に囲まれた盆地は、穏やかで土地の恵みを感じる。
ちょっと山を越えると、風も文化も変わる。そんな「福岡の離れの宿」の旅なのでした。














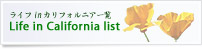
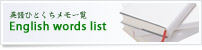
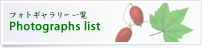

 Page Top
Page Top