グーグルさんのケータイ:いよいよ「G1」登場!
- 2008年10月30日
- 業界情報
Vol.111
グーグルさんのケータイ:いよいよ「G1」登場!
今月は、グーグルさんの新しいケータイ「G1」のご紹介に引き続き、間近に迫った大統領選挙と景気のお話などをいたしましょう。
<グーグルさんのG1>
 ご存じのとおり、10月22日の水曜日、アメリカでは待ちに待ったグーグルさんの携帯電話が売り出されました。
ご存じのとおり、10月22日の水曜日、アメリカでは待ちに待ったグーグルさんの携帯電話が売り出されました。
名付けて、「T-Mobile G1」。携帯キャリアのT-Mobile(ドイツ・テレコムの子会社)が提供しています。色は黒と茶色の2種類です。
言うまでもなく、G1は、グーグルさんが新しく開発した携帯電話OS「アンドロイド(Android)」を搭載しているわけですが、ハードウェアの方は、台湾のメーカーHTC製となっております。
HTCは、マイクロソフトのウィンドウズモバイルOSを搭載する端末をたくさん手がけてきた、スマートフォン分野のベテランとも言えるメーカーです。なんでも、HTCの社長であるピーター・チョウさんが、グーグル・モバイルプラットフォーム部門ディレクターのアンディー・ルービンさんと親しかったことから、両社のコラボレーションが実現したのだとか。
長い間「Gフォーン」というニックネームで取り沙汰された、栄えあるグーグルケータイ第一号機を作ったメーカーとしては、さぞかし鼻が高いことでしょう。
全米での発売に先駆け、前日の夕方、サンフランシスコのT-Mobileショップには、一足先にG1を購入しようと、たくさんの人たちが詰め掛けました。ショップの前の長蛇の列は、きっとネットでご覧になったこともあるでしょう。
けれども、その翌日、「いよいよG1をゲットするぞ」と近くのT-Mobileショップに出掛けた連れ合いは、がぜん拍子抜けしてしまいました。だって、ショップの中には、人っ子一人お客がいないのですから!!
え、誰もG1には興味がないの?
 そんなわけで、行列に並ぶこともなく難なく手に入れたG1ですが、連れ合い曰く、「これって、しょせんアップルのiPhone(アイフォーン)のコピーでしょ!」
そんなわけで、行列に並ぶこともなく難なく手に入れたG1ですが、連れ合い曰く、「これって、しょせんアップルのiPhone(アイフォーン)のコピーでしょ!」
いえ、さすがにグーグルさんの作だけあって、ネットアクセスは快適です。それに、グーグルさんのメールやコンタクツ(アドレス帳)やカレンダー(予定表)のシンクロ(パソコンとケータイ間のデータの同期)はとってもうまくいくのです。
でも、それ以外は、「あんまりうまくできていない」というのが、G1をチョイといじってみた感想だそうです。
まあ、見た目も、メニューのラインアップも、アップルさんの真似と言われても反論できない感はあるのですが、そのわりに、本家本元ほどうまくできていない、というのが正直な評ではないでしょうか。
 たとえば、基本的なボタンの使い方がわかり難い。連れ合いは、電源の入れ方がわからず、マニュアルを見て探し当てたそうです(右端の赤いボタンです)。それから、メールなどを操作していて、メニューの奥深くにどんどんと入って行った場合、「前に戻る」のボタンを発見するのに、えらく時間がかかったとか(電源の横の矢印ボタンです)。
たとえば、基本的なボタンの使い方がわかり難い。連れ合いは、電源の入れ方がわからず、マニュアルを見て探し当てたそうです(右端の赤いボタンです)。それから、メールなどを操作していて、メニューの奥深くにどんどんと入って行った場合、「前に戻る」のボタンを発見するのに、えらく時間がかかったとか(電源の横の矢印ボタンです)。
わたしは、電源ボタンはすぐにわかりましたが、カメラのシャッターに使うボタンがわかりませんでした。最初、間違って電源ボタンを押してしまって、画面が真っ暗になってしまいました。次に「これだろう」と真ん中のポッチを押してみたら、3秒ほどたって、ようやくカシャッと写真が撮れました(反応が遅くて、途中で動かしたのが悪かったみたいです。普通はもうちょっとスピーディーに撮れるようです)。
個人的には、日常的に使う電子機器は直感的でなくてはならないと思っているので、何のボタンであれ、マニュアルを見ないと操作できないようなものは、あまりできが良くないと思うのです。
 デザイン的には、なんとなく、同じくT-Mobileがティーン向けに出している「SideKick(サイドキック)」に似ていて、タッチスクリーン画面がパカッとスライドして、キーボードが出てくるようになっています。
デザイン的には、なんとなく、同じくT-Mobileがティーン向けに出している「SideKick(サイドキック)」に似ていて、タッチスクリーン画面がパカッとスライドして、キーボードが出てくるようになっています。
けれども、物理的なキーボードがあって良いかというと、必ずしもそうとは限らない。なぜなら、いちいち画面をスライドしてキーボードを出さないと文字が打てないから。でなければ、とっさにネット検索すらできないのです。おまけに、右側にある突起が邪魔になって右端のキーが打ち難い。
だったら、無理してキーボードなんか付けないで、iPhoneのように、画面上でタッチするバーチュアルキーの形式でいいのではないか?とも思えるのです。
 画質も、iPhoneの方が格段にいいですね。たとえば、こちらはYouTubeで見た同一のビデオクリップですが、左のiPhoneの方が、画面が断然きれいです。(すみません、画面に指紋が付いていて見辛いですね・・・)
画質も、iPhoneの方が格段にいいですね。たとえば、こちらはYouTubeで見た同一のビデオクリップですが、左のiPhoneの方が、画面が断然きれいです。(すみません、画面に指紋が付いていて見辛いですね・・・)
G1には、ネットを利用し易くするために、iPhoneのようにワイヤレスLAN(WiFi)機能も付いています。しかし、標準設定は3Gネットワーク接続となっているので、設定を変更しないと、近くにWiFiステーションがあっても、そちらには繋がらないのです(言うまでもなく、iPhoneの方は、WiFiを自動的に検知するようになっていますね)。
すると、うっかりそれを知らないで、海外に行ってローミングしているなんてことが起きるかも・・・(あとで請求書を見てびっくり?)
 それから、ちょっと盲点かもしれませんが、iPhoneではうまく生かされているアクセレロメーター(ジャイロスコープみたいに方向を検知する機能)が、G1では有効利用されていないのですね(内蔵はされているそうですが)。
それから、ちょっと盲点かもしれませんが、iPhoneではうまく生かされているアクセレロメーター(ジャイロスコープみたいに方向を検知する機能)が、G1では有効利用されていないのですね(内蔵はされているそうですが)。
だから、iPhoneを縦横に動かすと、画面が自然と縦長になったり横長になったりするところが、G1は、物理的にパカッとスクリーン画面をスライドしないと横長の画面にならないんです。
iPhoneの場合は、この機能を使って、ゲームを楽しむこともできますよね。
けれども、わたしは、この場でG1の悪口を言うためにこれを書いているわけではないのです。なぜなら、G1というグーグルフォーンがどんなものであれ、グーグルさんにとっては、その売れ行きはあんまり関係ないんじゃないかと思うから。
そりゃあ、グーグルさんにもチャレンジしなければならない課題はありますよ。たとえば、アップルさんのiPhone、iTunes、App Storeのように、ハードウェアとソフトウェアがシームレスに動き、もっとスムーズにサービスを提供するようにならないといけないと思うのです。
G1にも、アプリケーションやゲームを買えるMarketや、音楽を買えるAmazon MP3はあるけれど、「かゆいところに手が届く」までには到達していませんから。
 しかし、そんな細かい部分はどうであれ、グーグルさんにとっての最大のチャレンジは、ケータイソフトのアンドロイドを出したぞってところにあるのではないでしょうか。だから、オープンソースのソフトウェアでもあることだし、あとはグループ(Open Handset Alliance)のみんなが頑張って良くしてくれればいいやと思ってる部分があるんじゃないでしょうか。
しかし、そんな細かい部分はどうであれ、グーグルさんにとっての最大のチャレンジは、ケータイソフトのアンドロイドを出したぞってところにあるのではないでしょうか。だから、オープンソースのソフトウェアでもあることだし、あとはグループ(Open Handset Alliance)のみんなが頑張って良くしてくれればいいやと思ってる部分があるんじゃないでしょうか。
アップルさんと違って、グーグルさんはケータイで儲けようなどとはまったく考えていないでしょう。第一、アンドロイドはロイヤルティー(ソフト使用料)を取っていないんですから。だから、長い目で見ると、一号機のG1が売れようが売れまいが、グーグルさんにはあまり関係のないことかもしれません。
きっと彼らにとっては、新しいことを成し遂げること自体が、楽しいチャレンジなのでしょう。たとえば、アンドロイドのように、自分の息のかかった新しいケータイソフトを世に広めて行くこともそうでしょう。現に、HTCに続いて、ケータイメーカー世界第3位のモトローラもアンドロイド採用を表明していますし、もしかすると、広まるのは時間の問題なのかもしれません。
けれども、もっともっと大きなこと、たとえば、月に探査機を打ち上げるとか、映画『2001年宇宙の旅』に出てきたHALみたいなコンピュータを作り上げるとか、そんなことも彼らにとってはワクワクする楽しいチャレンジのひとつなのでしょう。
そういうことですので、現時点でG1をうんぬんするのは、あまり意味がないような気もしているのです。
<いったい誰が払うの?>
さて、お次は、景気のお話です。9月中旬、ウォールストリートを震源地として全世界に広まった金融危機は、困ったことに、庶民の間にも確実に広がりを見せているようです。
 たとえば、比較的経済が安定しているシリコンバレーでも、個人破産をするケースが増えていて、7月から9月の四半期では、前年に比べてほぼ倍のペースとなっているそうです。お陰で、昨年一年間で4千件強だったところが、今年は9月の時点で、すでに5千件を軽く越えているのだとか。
たとえば、比較的経済が安定しているシリコンバレーでも、個人破産をするケースが増えていて、7月から9月の四半期では、前年に比べてほぼ倍のペースとなっているそうです。お陰で、昨年一年間で4千件強だったところが、今年は9月の時点で、すでに5千件を軽く越えているのだとか。
ざっくり言って、シリコンバレーの人口は2百万人くらいなので、年間数千件の個人破産と言っても、決して無視できる数字ではないでしょう。その多くは、住宅バブルに乗って購入した家の価値が、抱えているローン額を大きく割り込んだことによるもので、貸し渋りをする銀行側ともローンの借り直し交渉がうまく行かず、仕方なく破産となってしまうようです。
そして、そんな不動産物件はどんどん市場に出回り、ますます値崩れを起こす・・・
破産とまでは行かなくとも、株式市場の壊滅的な暴落のお陰で資産が大きく目減りし、そのことが人々の心に大きな翳を落としています。すでにリタイア(退職)している人からは「また働かなくっちゃ食べていけない」という不安の声がもれていますし、ティーンエージャーを抱える親たちからは「希望の大学ならどこでも行っていいよと、子供に自信を持って言えない」といった悲観的な声も聞こえています。
投資の神様であるウォーレン・バフェット氏は、「今は、下がりに下がったアメリカ企業の株が買い時だ。わたしはどんどんアメリカ株に投資する」とおっしゃっているのですが、そうしたくても、庶民にとっては、株を買うお金もありません。
下手に投資なんかすると、日に日に目減りするので、「ベッドのマットレスに隠した方がいいや」と、ジョークとも本音ともつかないようなヤケッパチの発言を耳にしたりします。(アメリカの場合は、お金の隠し場所はタンスの引き出しじゃないんですね!)
 ジョークと言えば、わたしの大好きな深夜コメディー番組『ジェイ・レノー・ショー(The Tonight’s Show with Jay Leno)』では、ホストのジェイ・レノーさんがこんなことを言っていました。
ジョークと言えば、わたしの大好きな深夜コメディー番組『ジェイ・レノー・ショー(The Tonight’s Show with Jay Leno)』では、ホストのジェイ・レノーさんがこんなことを言っていました。
「あなたがチョンボすると、あなた自身が尻ぬぐいをする。しかし、彼らがチョンボすると、やっぱりあなたが尻ぬぐいをすることになるんだよね。(If you screwed, you pay. If they screwed, you pay.)」
レノーさんが言う「彼ら」というのは、ウォールストリートの銀行屋さんのことですが、彼らが好き勝手にやって(世界中の)経済をめちゃくちゃにしたのに、彼ら自身ではなく、税金を払ってる庶民がツケを払うことになる、という熱いメッセージなのです。
連邦議会では、財務長官の音頭取りに乗って、少なくとも7000億ドル(約70兆円)の公的資金の投入を決めたわけですが、この論理は、庶民にとっては、自分たちの血税から銀行屋に対して信じられない額のサラリーやボーナスを払っているとしか映らないのですね。
たしかに、破綻が決まって、何十億円という「さよならボーナス」をもらった銀行トップはたくさんいて、どうしてそうなるのかと、頭を抱えるしかないのは事実です。
けれども、わたしにとっては、そもそもいったいどこに金融界に投入するお金があるのかと、疑問視せざるを得ないのです。もちろん、公的資金は必須だとは思いますが、その出所はいったいどこなんでしょう?
ブッシュ大統領になって、早8年。その間に、アメリカの財政は急激に悪化し、今は、毎年赤字に次ぐ赤字という状態です。
9月末に終わった2008年度には、史上最悪の財政赤字(budget deficit)となる4550億ドル(約46兆円)を記録しています。これは、イラク戦争を始めたせいで、それまでの赤字記録となった2004年度の4130億ドルを塗り替える結果ともなっています。
お陰で、国が抱える負債(national debt)はどんどん膨らみ、現在は10兆ドル(約千兆円)という規模。今の時点で、負債の比率はGDPの7割にもなっているのに、新たに7000億ドルの投入を行えば、もっともっと負の財産が増えていく・・・これって、アメリカがどんどん借金地獄にはまっていくってことでしょう。
この困った状況をジ~ッと睨んで、おもしろい事を言い出した人がいます。「いっそのこと、金持ちがみんなでお金を出し合ったら?」と。
これは、シリコンバレーの地元紙、サンノゼ・マーキュリー新聞のコラムニストであるマイク・キャシディー氏が書いていたことなのですが、フォーブス誌が発表した「金持ちトップ400」のリストを眺めていて、こんなことを思い付いたそうです。
この400人全員が自分の資産の半分を出し合ったら、ちょうど公的資金の7000億ドルになるじゃないかと。
なんでも、400人の総資産は、実に1兆5700億ドル(約157兆円)。だから、みんなが半分ずつ出し合ったら、7000億ドルなんて軽いものでしょうと。(ちなみに、1兆6000億ドル近くなんて額は、クリントン大統領時代のアメリカの国家予算に匹敵するものなのです!!!)
普段、わたしは、このキャシディー氏の意見には賛同しないことが多いのですが、このときばかりは、「なるほど、妙案だ!」と、膝を打つことになりました。
だって、このリストの中で一番「貧乏」な人でも、資産は13億ドル(約1300億円)。半分に目減りしたって、6億ドル(約600億円)は手元に残るんですよ。そんな額は、一生かかったって使えやしません。
まさか墓場に札束を持って行くわけにはいかないし、それだったら、いっそのこと、困っている国民のためにポンと出してあげたらいかがでしょう? そうすれば、自分だって、「人助けをしたぞ」と、いい気分になれるでしょうに。
 残念ながら、そんな奇特な人はほとんどいないとは思いますけれど、自分の資産の8割をビル&メリンダ・ゲイツ財団に投げ出した、ウォーレン・バフェット氏という実例だってあるではありませんか。
残念ながら、そんな奇特な人はほとんどいないとは思いますけれど、自分の資産の8割をビル&メリンダ・ゲイツ財団に投げ出した、ウォーレン・バフェット氏という実例だってあるではありませんか。
経済構造がここまでゆがんでしまった以上、誰かがまともなことをしないと、どうにもならないところまで追い詰められていると思うのですけれど・・・
というわけで、お次は、間近に迫った大統領選挙のお話をいたしましょう。
<脳と政治>
世の中には、ざっくり言って、ふたつのタイプの人間がいるのでしょう。ひとつは「かっこいい、クールな」商品を目ざとく見付けて、そちらに釘付けになるタイプ。そして、もうひとつは「かっこ悪い、ダサい」商品を見付け出し、そちらの方にどうしても気を取られるタイプ。
これは、ファンクショナルMRI(fMRI)を使って人の脳の働きを研究しているカリフォルニア工科大学のグループの研究成果でもあるのですが、脳の無意識の反応によって人間を大別すると、瞬時にかっこいい物を識別し、「ああいうのっていいなあ」と好感を抱くタイプと、逆にかっこ悪い物に反応し、「ああいう風にはなりたくないものだ」と拒絶を示すタイプと、ふた通り存在するということです。
前者は、「あんなクールな物を持ってると、人にかっこよく見られるよなぁ」と感じるタイプ。そして後者は、「あんなダサい物を持ったら、みんなにかっこ悪いって思われるじゃん」と決め込むタイプ。そう、人間は社会動物であるがゆえに、人にどう見られているのかが頭の隅でいつも気になっている生き物なんですね。
このような人の分類は、昨今注目を浴びつつある「ニューロマーケティング(Neuromarketing、脳に直接訴えかけるマーケティング)」の研究テーマのひとつでもあるのですが、個人的には、この二種類の人の大別は、政治の世界にも通用するのではないかと思っているのです。
つまり、世の中には、かっこいいものに強く反応するタイプの候補者と、かっこ悪いものに強く反応するタイプの候補者と、ふた通り存在するのではないかと。
すなわち、有権者に向かった選挙キャンペーンにおいても、自分の「かっこいい」政策を打ち出し、自らのクールさを訴えるのか、それとも相手の「かっこ悪い」弱点をあげつらい、相手のダサさを攻め立てるのか、候補者がどちらのタイプかによってキャンペーンの仕方がまったく異なってくると思うのです。
 いよいよ11月4日に迫るアメリカの大統領選挙ですが、現在、両候補が採っているアプローチは、きれいに二手に分かれると見ています。
いよいよ11月4日に迫るアメリカの大統領選挙ですが、現在、両候補が採っているアプローチは、きれいに二手に分かれると見ています。
民主党のバラック・オバマ氏は前者、つまり自分のクールな政策を主に打ち出すタイプ。そして、共和党のジョン・マケイン氏は後者、つまり相手のダサい弱点をあげつらうタイプ。
たとえば、オバマ氏は、こう訴えます。ここで8年も続いたブッシュ政権のしがらみを打破しよう!そのためには、金持ちを優遇する不公平な税制を改革し、中流階級や低所得層の負担を軽減しようじゃないか。自分にはそれを実現する具体案もあるし、実行力もあるのだと。
それに対し、マケイン陣営は、「オバマ氏は危険なほどに青二才で、彼じゃ大統領になっても何もできないんだよ」と、否定的に訴えます。
そして、金融危機の嵐がアメリカ中を襲い、いよいよ経済音痴のマケイン氏が形勢不利になってくると、「オバマという奴は、1960年代にFBIがテロリストの地下組織と認定したグループと深い付き合いがあったのだ」と、テロに対する有権者の恐怖心を扇動する心理作戦に出ます。
さらに、オバマ氏が経済救済策の理念を説くと、「彼は銀行を国営化しようとしている社会主義者だ」と、アメリカ人の大嫌いな「社会主義」という言葉を巧みに駆使するのです。
今では、マケイン支持者の間では、オバマ氏に対する「危険人物」「テロリスト」「アラブ人(イスラム教徒を示唆する言葉)」「社会主義者」「共産主義者」といったレッテルが独り歩きしています。
よくもまあ、恥ずかし気もなくウソを並べ立てるものだと、こちらは不快感を通り越して感心すらしてしまうわけですが、アメリカという国は、とにかくでっかい不思議な国でして、ひと口で「こうだ!」とはステレオタイプ化などできないのですね。だから、有権者も実にいろいろ。
たとえば、アメリカの各種研究機関は、ノーベル賞を受賞するような優れた研究者を育む素地を持ち、そこには天才ともいえるような卓越した人材が集ってきます。わたしの知り合いの男の子などは、たった14歳でコミュニティーカレッジを卒業し、コンピュータを人間の脳に近づける研究をしているグループに招かれ、この秋、カリフォルニア大学バークレー校の3年生に編入しています。
その一方で、一桁の足し算や引き算も危うい人や、「地球は5千年前に神によって7日間で造られた」と、本気で信じている人もたくさんいるのです(共和党副大統領候補のサラ・ペイリン氏などは、このクチですね)。
そして、後者のタイプの人たちは、自分の脳細胞で独立独歩に物を考えようとしないから、選挙キャンペーンの扇動にコロッと乗せられてしまう・・・
けれども、そんな悪口作戦は、もう風前の灯(ともしび)かもしれません。現時点での世論調査からいくと、前回2004年の大統領選挙で共和党のブッシュ大統領に傾いた州でも、今回は民主党のオバマ氏支持に翻(ひるがえ)りそうな州はたくさんあるようです。
そういった寝返り現象は、そのまま、今回の選挙に対する有権者の関心の高さを表しているのでしょう。今までは、ともすると、若い人や有色人種、そして社会の底辺にいるような人たちは、投票する関心や機会がないケースが多かったのです。けれども、そんな風に投票に縁のなかった人たちも、今回ばかりは有権者の登録(voter registration)を済ませ、実際に投票する意気込みでいるようです。
 カリフォルニア州のような大きな州でも、実際の投票率(turnout)は、登録者の85%まで伸びるのではないかと期待されています。(写真は、シリコンバレーのあるサンタクララ郡の広告で、有権者に投票を促すもの。)
カリフォルニア州のような大きな州でも、実際の投票率(turnout)は、登録者の85%まで伸びるのではないかと期待されています。(写真は、シリコンバレーのあるサンタクララ郡の広告で、有権者に投票を促すもの。)
そう、昔は、投票率は高かったんですね。カリフォルニア州では、1952年から1976年の間に行われた7回の大統領選挙では、すべて8割を超えていたそうです。
ちょうどその頃は、アメリカ自体が大きな変革を遂げている時代でした。第二次世界大戦後のソビエト連邦との冷戦、ひと筋の明かりだったケネディー大統領の暗殺、黒人の権利と平等を訴える公民権運動の激化とキング牧師の暗殺、そして、ヴェトナム戦争。まさに荒海とも言えるような世相だったのでしょう。だから、多くの有権者が、投票して世を変えたいと望んでいた。
そして、今回も、荒海の真っただ中なのかもしれません。そう、金融危機と社会・経済構造に対する信用失墜の荒波。
そんな世相を反映して、国中の投票率はグンと伸びるのでしょうが、伸びた分のほとんどは、民主党のオバマ氏に流れることでしょう。「ストレート・トーク(まっすぐに物を言うこと)」で知られるマケイン氏が悪口作戦に出るなんて、幻滅を感じる国民も多いでしょうから。
思えば、今のブッシュ大統領という人は、歴代の大統領の中でも最も悪運の強いお方なのでしょう。2005年8月にルイジアナ州を襲ったハリケーン・カトリーナが、もしもその前年に起きていたのならば、2004年の大統領選挙では彼が再選されることはなかったでしょう。
しかし、あの大惨事とそれに続く政権の大失態は、ブッシュ大統領の二期目が始まった後に起こった。これはまさに、神の悪戯(いたずら)としか言いようのないタイミングでした。
 けれども、今回は、金融危機という未曾有の大混乱が全世界を襲い、経済構造の根本的な建て直しが迫られている。そんな中では、庶民の味方とのイメージが強い民主党が中心となって政治を進めることが望まれているし、経済政策にも明るいオバマ氏が大統領候補としての名声を高める結果ともなっています。
けれども、今回は、金融危機という未曾有の大混乱が全世界を襲い、経済構造の根本的な建て直しが迫られている。そんな中では、庶民の味方とのイメージが強い民主党が中心となって政治を進めることが望まれているし、経済政策にも明るいオバマ氏が大統領候補としての名声を高める結果ともなっています。
しかも、皮肉なことに、8年間に渡るブッシュ大統領の悪政が、オバマ氏の大きな追い風ともなっているようです。
今回ばかりは、勝利の女神はオバマ氏ににっこりと微笑んでいるのでしょう。
夏来 潤(なつき じゅん)
本が出ました!
- 2008年10月21日
- エッセイ
そうなんです、執筆を担当していた本が、ようやく日本の本屋さんに並びました。
この本は、わたしがゴーストライター(出版界では構成者と呼ばれる)として執筆を担当した本なのですが、13年前に日本からシリコンバレーに渡って、コンピュータ・ソフトウェアのスタートアップ会社を経営陣のひとりとして守り立て、ナスダック株式市場への株式公開や参入した分野での市場独占を果たした、日本人ビジネスマンの体験談となっております。
題して、
荒井真成氏著 『世界シェア95%の男たち 〜 IT創成期を勝ち抜いた企業の“光と影”』(イースト・プレス発行)
まあ、世の中にビジネスの本はたくさんありますが、こちらは単純にサクセスストーリーとはいかないところがミソだと思うのです。
何と言いましょうか、山あり、谷ありのアップダウンの連続。そんな感じかもしれません。
まず、ご本人である荒井真成(あらい・まさなり)氏は、もともと英語がまったくダメな方でした。シリコンバレーに渡る前に、フロリダに2年半駐在した経験があるのですが、その最初の半年は、からきしコミュニケーションができなくて、胃が痛くなるほどに苦労なさったとか。
フロリダなんて、カリフォルニアのようにアジア人が多いわけじゃないし、日本人の英語なんてまったくわかってくれない。だから、人と話をしていて行き詰ると、最終的には、筆談やメールで難を乗り切っていたのでした。
けれども、不思議なもので、半年を越えると、だんだんと相手の言うことが聞き取れるようになって、こちらも言いたいことを言えるようになってくる。そうなると、だいぶ仕事もやり易くなるし、仕事を楽しむ余裕も少しずつ出てくるものなのですね。
そうやって意思疎通の難関はくぐり抜けたものの、シリコンバレーにやって来たときは、いきなりスタートアップ会社の副社長として、経営陣の仲間入りをしなければなりませんでした。
それまで、日本ではマネージャーの経験すらないのに、いきなり経営者のひとりとして、自分自身でバンバンと英断を下さなくてはならない。いかに小さな、10人ほどの零細企業とはいえ、経営者のひとりとなると、一スタッフとして働くのとは大きく違います。
でも、そこは自分でいろいろと考えて、工夫して、慣れるしかない。そうやって試行錯誤を繰り返していくうちに、鋭い判断力も培われていくもののようですね。
シリコンバレーという環境にある程度救われた部分があるとするならば、こちらのスタートアップ会社には、新しいものにどんどんチャレンジする不屈の精神がみなぎっていたことでしょう。失敗をしても、そんなものは一過性のものでしかないし、次にまた頑張ればいいや、といった楽観主義的な空気に満ちていた。それに、試してみたい新しいアイディアは、次から次へと湧いてくる。
まさに「失敗は成功のもと」であり、失敗しても個人が理不尽に責められることはない。
とくに荒井氏が参画したプーマテクノロジー(のちにインテリシンクと改名)というスタートアップには、厳しい中にあっても、「仕事を楽しむ」精神がみなぎっていたのかもしれません。
おかしな話なのですが、荒井氏の近しい仲間となった創設者のふたりが、賭けをしていたことがありました。シリコンバレーにやって来た荒井氏が、果たしていつ経営者としての最初の英断を下すのかと。
ひとりは「一ヶ月以内」に賭け、もうひとりは「一週間以内」に賭けました。結果的には「一ヶ月以内」が勝って、賭け金100ドル(約1万円)を手にしたわけではありますが、これにしたって、仕事を必要以上にシリアスに考え過ぎない態度が如実に現れていると思うのです。(このエピソードは、第10章「シリコンバレーが熱かった日々」に紹介されています。)
それでも、文化が違うゆえに、アメリカと日本の狭間に立って、苦労なさることはたくさんあったようです。わたし自身も、シリコンバレーのスタートアップ会社で痛感したことがあるのですが、日本の「品質」に対する期待は、アメリカとは比べものにならないくらい高いものなのです。
だから、アメリカ人のエンジニアが「どうしてこれじゃいけないの?」という部分と、日本人の顧客が「こんなんじゃ買えませんよ」という部分の大きな溝を、間に立った人が少しずつ埋めていかなくてはならない。
そして、それは端で見ているよりも、もっと難しい骨の折れることなのですね。
現に、天下のNTTドコモを相手にして、「iモード」向けのサービスで大失態をしでかしたこともあるし・・・(詳細は、第16章「携帯電話時代を予見した戦略」に出てきます。)
この本は、あくまでもIT企業をベースとしたお話なので、赤外線を使った通信ソフトウェアだの、データベースを同期するソフトウェア製品だのと、ちょっと技術的な内容が出てきます。若い方は見たこともないような、PDA(Personal Digital Assistant)という携帯情報端末機が出てきたり、お仕事でしか使わないようなソフトウェアの名前が出てきたりもします。
それから、インターネットという新しい媒体が登場すると、それまで個々のパソコンや携帯端末に特化していた商売を、ネットを利用した幅広いサービスに広げようといった新しい試みも出てきます。
そういうわけで、IT業界に縁の薄い方には、読んでいてちょっと面倒くさい部分も出てくると思うのですが、そういうところは全部すっ飛ばして、次のページに進んでいただければいいなと切に願っているところです。
何を思ったのか、気が付いたらいつの間にやら日本からアメリカに飛び出していた、一ビジネスマンのお話。そんなストーリーを拾い読みしていただければありがたいと思っているのです。
たとえば、こんなことを読み取る方もいらっしゃるかもしれません。
宣伝するお金さえあれば物は売れる(?)。じゃあ、そんな余裕のない会社は、物は売れないの? いえいえ、そんなことはありません。工夫さえすれば、販路は開けるものなのです!
それから、こんなことを感じ取る方もいらっしゃるかもしれません。
もし技術力が足りなかったら、いったいどうやって製品を開発すればいいの? いえいえ、一からすべて自分で作ることはないでしょう。自身でできなければ、どこかから技術を買ってくればいい。それもシリコンバレー流の開発の仕方なのですよ。
こんな風に、いろんなお話が詰まっているので、読む方の経験や興味のありどころによって、さまざまな違った読み方ができると思うのです。
だから、たくさんの方々に読んでいただければいいなぁ、と願っているところなのです。
だって、せっかく頑張って書いたんですものね。
色
- 2008年10月14日
- エッセイ
前回のエッセイ「音」では、日本の夏の音ともいえる、蝉の声のお話をいたしました。
今回は、色のお話をいたしましょうか。
8月の終わり、2週間の滞在を終え日本から戻って来ると、我が家にたどり着いて、まず思ったことがありました。
「光が金色!」
成田から到着したサンフランシスコ空港は、いつもの事ながらちょっと霧がかかっていたのですが、シリコンバレーに南下するにつれてだんだんと霧も晴れ、サンノゼの我が家に着く頃には、あたりはもう太陽の光でいっぱい。そして、見るもの、見るものすべてが金色に輝いて見えるのです。
日本の夏も光線はかなり強いですが、カリフォルニアの光線はなお強い。だから、木々や花々に当たる光が、キラキラと金色(こんじき)に跳ね返って目の中に飛び込んでくるようです。ちょうど、光が物体の上で踊ってでもいるような感じでしょうか。
そして、光はそこら中に充満し、辺りは金色のヴェールに包まれるかのように輝いて見えます。
そこで思ったのですが、いろんな国によって、光の色って違うのだろうなと。
そういえば、アメリカに住み始めて最初に日本に里帰りしたとき、着陸を控える飛行機の窓から見えたのは、深い緑でした。
成田空港のまわりはこんもりとした森の多い所ではありますが、その森の緑は、決してアメリカではお目にかからない類(たぐい)の緑でした。アメリカの緑は、もっとカラカラに乾いた感じとでも言ったらいいのでしょうか。それに比べて、日本の緑はしっとりとしていて深みがある。
祖国を目の前にして、そのように感じたのは、実は、わたしだけではなかったようです。日本画の巨匠である故・東山魁夷(ひがしやま・かいい)画伯は、留学先のドイツから帰国したときのことをこう述べておられます。
「群青(ぐんじょう)と緑青(ろくしょう)の風景だ」と私は思った。「それにしても、なんと可愛らしく、優しく、こぢんまりとまとまっているのだろう」
(中略)
空は晴れていた。海は青かった。しかし、地中海のコバルトやウルトラマリンではなく、白群青(びゃくぐんじょう)や群青という日本画の絵具の色感だった。花崗岩質の島を蔽(おお)う松の茂みは、緑青を塗り重ねた色そのままに見えた。空気は爽やかな中に、潤いと甘やかさを持ち、ほっとするような安らかさと、親しさに満ちていた。
(講談社文芸文庫・現代日本のエッセイ『泉に聴く』より。同書187ページの「東と西 I」を引用。)
これは、昭和10年(1935年)の秋、2年間の欧州滞在を終え、ナポリからの船が瀬戸内海にさしかかったときの印象だそうです。いかにも日本的な風景が、もの珍しく感じられたとも書いておられます。
画伯は、専門の日本画のみならず、文筆にも秀でた方だったので、わたしが初めて里帰りしたときの感覚も、絵具の名を使って的確に表現してくださっているように思います。
そう、日本の色って、外国とはぜんぜん違うんですよね!潤いを含んだ、まったりとした感じ。画伯のおっしゃるように、「ほっとするような安らかさと、親しさに」満ち溢れ、戻って来る者を安堵させる色。
やはり、光というフィルターを通すと、似たような色でも、かなり違って見えるのではないでしょうか?
そして、そんな風に光を感じたのは、日本人だけじゃないんですね。
そう、場所は、遠く離れたフランス。
時は、19世紀末。
登場人物は、絵描きのクロード・モネ(Claude Monet)。
その頃花開いた「印象派」の画家たちは、それまでの絵の技法や決まり事にとらわれず、自分で感じたままを自由に表現した人たちでした。中でも、その中核をなす画家クロード・モネは、「光」をとっても大事にした人でした。
モネは、部屋の中にお行儀よく座るモデルや、机に並べた花瓶や果物ではなく、屋外の自然を好んで題材にしました。風にたなびく草原や、岩場に打ちつける波、そして、勢いよく噴き出す機関車の蒸気と、動きのある景色が彼の心を強くとらえるのです。
わたし自身は行ったことはありませんが、きっと光溢れるフランス南東部のプロヴァンス地方には、彼のお気に入りの景色はたくさんあったことでしょう。
そんな風に自然とじっくりと向かい合う彼は、あるとき、「風景画」というものが存在しないことを悟るのです。
なぜなら、刻々と変わる太陽光線の加減によって、目の前の風景も色を変え、姿を変え、決して制止するものではなかったから。このように、風景とは際限なく存在するものだから、一枚の絵をもってして「これがここの風景です」なんて断言はできないと感じたのですね。
ときに、ふと畑で足を止め、干草の山を描いたことがあります。このときは、2枚のキャンバスを並べ、ほぼ同時に描き始めました。一枚は、日が翳ったときのグレーの絵、そしてもう一枚は、雲が晴れ、辺りが光で満ち溢れているときのカラフルな絵。
そのうち、日が西に傾き、光にオレンジ色が混じるようになります。すると、3枚目のキャンバスを並べ、素早く描き始めます。そう、こちらは、紅(くれない)の夕日に映える干草の山。まるで地平線に落ちる太陽と競争するかのように、筆をリズミカルに運んでいきます。
そんな屋外の経験を積んでいくうちに、光によって姿を豹変する対象物をシリーズ物として描くようになりました。
代表的なものに、寺院(ルーアン大聖堂)や川沿いのポプラ並木などがあります。ルーアン大聖堂は、ブルー、ピンク、黄色といろんな色を基調として、次から次へと30枚も描いたそうです。
そして、睡蓮も。モネというと、まず池に浮かぶ睡蓮の絵を思い浮かべるほどに、お気に入りの題材のひとつだったようですね。
この睡蓮の池は、モネが亡くなるまでの43年間住んでいた、ジヴェルニーの家の向かいにありました。
これはモネ自身がデザインしたもので、もともと湿地帯だった所に付近の川を引き込んで造りました。近くの大工に造らせた日本風の太鼓橋も、なくてはならないアクセントとなっています。自らの手で築いたこの楽園を、彼は何よりも愛していたのかもしれませんね。
チラチラと輝く水面、かぐわしい花を開かせる睡蓮、風にゆらゆらと吹かれる柳の枝と、どれをとっても刻々と変化する題材に、画家としてのチャレンジ精神を駆り立てられていたことでしょう。
このモネという人は、あまりにも光にこだわっていたために、ひとり目の奥さんが病気で死の床にあるときも、彼女の顔に当たる日の光をとらえてみたいと、キャンバスと絵の具を引っ張り出したくらいです。
けれども、それは決して芸術家の奇行などではなく、光によって移りゆく「瞬間」というものを自分の手でとらえたいという、画家の魂の表れなのではないでしょうか。
晩年、モネは、同じく印象派の天才画家で、やはり風景画を好んで描いていたセザンヌと自身を比較し、ふたりの間にはこんな違いがあるのだと説明しています。
「僕たちふたりは、自然を追い求めていたんだ。けれども、彼は自然を(キャンバスの中に)構築して、それをそのまま保存しようとしたのに対し、僕にとっては、一瞬、ただそれだけだった。決して二度と戻らない瞬間を追い求めているんだよ」と。
なるほど、そうやって考えてみれば、景色は光によって刻々と変わるものなんだと、子供の頃から何となく悟っていたような気もしますよね。
夕暮れの頃、家に帰るのも忘れて、辺りの色の変化をボ~ッと眺めていたことがありませんか?それは、やはり、行き過ぎる一瞬一瞬を見逃したくないから、じっとそうやってたんじゃないでしょうか。
誰だって、子供の頃は、光を追う芸術家だったのかもしれませんね。
そして、本物の芸術家は、瞬間を追い求めて、終わりのない旅に出る。なぜなら、自分の芸術には完成などないことを知っているから。
追記: クロード・モネの作品「睡蓮の池と橋」と、当時の池と本人の写真は、ベラジオ美術館(米ネヴァダ州ラスヴェガス)の展覧作品カタログ “The Bellagio Gallery of Fine Art: Impressionist and Modern Masters”(Libby O. Lumpkin, ed., 1998)を撮影させていただきました。
モネの作風については、英BBCが2007年に制作した『Impressionists(印象派の画家たち)』という長編ドラマを参考にいたしました。ドラマ仕立てではありますが、本人たちの書簡やインタビュー、当時の新聞記事などに基づき、史実を忠実に再現しているようです。
蛇足となりますが、モネが最初に絵画学校に入ったとき、クラスメートの中には、後に有名人となるピエール・オーギュスト・ルノワールと、繊細な表現法を持ったフレデリック・バジールがいました。3人はとても仲が良くて互いに励まし合っていたのですが、バジールは29歳の若さで、参戦したプロシアとの戦争で命を落としてしまいます。
モネたち3人組は、少し年長のエドゥアール・マネとエドガー・ドガとも親交を深めていくのですが、やがて、そこに加わったポール・セザンヌを含めて、仲間内の展覧会を開くようになります。これが後に、当時の画壇を牛耳っていたサロンをひっくり返すほどの名声を得て、「印象派」と呼ばれる一派に大成していくのです。
なんでも、「印象派(Impressionism)」という言葉は、第3回の展覧会(1877年)を描写した「印象が薄い(unimpressive)」という辛口の批評からきているんだそうです。それくらい、最初のうちは大不評だったようですね。
それでも、そんな逆境に負けないで、仲間内で切磋琢磨し合った。そして、それが、印象派の画家たちの成長と成功に結び付いたわけですね。学術的な研究もそうだと思いますが、仲間というものは、何か新しいものにチャレンジするときに大きな力を発揮してくれるものなのでしょう。
9月中旬、シリコンバレーはまだまだ暖かいというのに、風邪をひいてしまいました。ご近所さんのディナーにお呼ばれして、そこで人にうつされてしまったのです。
近頃、自家製ヨーグルトを毎朝食べるようになって、とんと風邪などひいていなかったのですが、よっぽど風邪のバイキンが強かったのでしょう。それとも、やはり風邪をひいている人と数時間もお話ししていたのがいけなかったのでしょうか。話しているときは、とっても楽しかったのに。
こちらシリコンバレーでは、9月に入ってもう風邪が流行っていて、鼻はズルズル(runny nose)、咳はゴホゴホ(cough)、そして熱を出して(run a fever)、体のあちこちが痛む(muscle aches)人もたくさんいるようです。今回の風邪はしつこくて、なかなか治らないという噂も耳にします。
わたしの場合は、鼻がズルズルするわりに、夜になると鼻がつまって(stuffy nose、もしくは nasal congestion)よく眠れないのです。それに、咳は出ないかわりに、喉が痛くて(sore throat)、痰(mucus)がひどかったですね。
結局、風邪で2日間は寝込んでしまったのですが、そんな中、タイミング悪く目医者さん(optometrist)の予約が入っていたのでした。コンタクトレンズを使っている人間の宿命でしょうか、毎年一回、目の検査をしてもらって、一年分のコンタクトレンズを買ったり、眼鏡を新調したりするのです。(ちなみに、目の病気になって、手術をするとなると、こちらのoptometrist ではなく、ophthalmologist に会いに行くことになりますね。)
そこで、予約をずらしてもらえないかと目医者さんのオフィスに電話をしたのですが、ここでちょっとびっくりすることがあったんです。
風邪で具合が悪いことを説明したあと、第一、まだ人に病気をうつす恐れがあるから、無理にそちらに行かない方がいいですと言ってみたのです。そう、こんな風に
I’m still contagious, so I don’t want to spread the cold virus to other people.
(ひとつ目の句に出てくる形容詞 contagious は、「伝染する病気を人に感染させる」という意味で、I’m still contagious というと「わたしはいまだに、人に病気をうつす感染性がある」ということです。ふたつ目の句の the cold virus というのは、風邪のウイルスのことで、句全体は「わたしは他の人に風邪のウイルスを広めたくない」という意味になりますね。)
すると、相手はこれに驚いてしまったのです。そんなに気配りをする人はいませんよと。
なんでも、普通はこうやって電話をかけてくるそうです。「今、風邪をひいて会社を休んでいるから、この絶好の機会に目医者さんに会いたいんだけど」と。
けれども、そう言われたら、いい気はしないのが人情でしょう。「わたしたちはいったいどうなるのよ?(What about us ?)といつも思ってしまうわ」と、相手の方はおっしゃっていました。
そこで思ったのです。目医者さんのオフィスに勤めるのも命がけだなって。健康な人なら、べつに風邪くらいで死んだりはしないでしょうけれど、それでも、患者さんにうつされたり、自分の家族にうつしたりと、何らかの迷惑を被る事は確かですよね。(現に、後日、目医者さんのオフィスに行くと、スタッフのひとりが風邪をひいていて、息子にもうつしてしまったと言っていました。)
どうしてみんな基本的な気配りができないのかなぁ?
まあ、アメリカでは、よく問題になるんですよね。風邪(the common cold)やインフルエンザ(flu)をひいているのに、会社や学校に無理矢理出てくる人が多いことが。それって、人にうつすことを何とも感じていないのでしょうか、それとも、仕事や学業を休んで遅れを取ることが何よりも恐いのでしょうか?
確かに、アメリカ人は、世界でも一番「働け、働け」というプレッシャーが強い国民ではないかと思うのですよ。「生産性(productivity)」の虜(とりこ)になって、自分のアウトプットが常に気になる宿命を背負った、余裕のない国民・・・
おっと、またまた話が逸れてしまいましたが、題名になっている cold season 。表題の部分にも書かれているとおり、「風邪のシーズン」という意味ですね。
そして、この言葉を聞くと、いつも自分自身のおもしろい体験を思い出してしまうのです。
10月に入ったある日、オフィスで同僚と話していて、「もうすぐ寒い季節になるねぇ」と言いたいことがありました。四季のはっきりしないシリコンバレーにも、ひんやりとした秋風が立ち始めた頃でしたから。
そんな風流な気持ちを持ちながら、わたしは、It’ll be cold season very soon と言ってみたのです。
すると、どうも相手は大きく勘違いしたようで、いきなり、風邪の話を始めたのです。風邪をひくと、熱が出たり、咳が出たりとイヤだよねぇと。
そう、ここでの教訓は、cold season と言うと、気候のことばかりではないということなのです。
もちろん、寒い季節のことを cold season と表現することもあるようです。たとえば、Gear up for the cold season と言うと、「寒い季節に向けて準備しなさい」という意味になりますね。
けれども、やはり勘違いする人がいるということを考えると、cold season の代わりに、cold weather(寒い天気)とか、cold winter months(寒い冬の時期)とか、違った表現を使うべきだったのでしょう。
たとえば、こんな風に。
The weather gets cold pretty soon.
(気候はもうすぐ寒くなりますね。)
We’re expecting cold winter months ahead.
(これから寒い冬の季節がやって来ますね。「winter months」は直訳すると「冬の月間」ということですが、日本語では「時期」とか「季節」の方が適切ですよね。)
単に「冬」という表現だけでもいいかもしれません。
The winter is definitely on the way.
(冬は確実に近づいています。「on the way」というのは、「途中にある」という意味ですね。こちらの文章は、ハリー・ポッターの映画に出てきた表現でした。)
それから、もっとはっきりと区別を付けるために、「風邪の季節」という意味の cold season を使うときは、cold and flu season、つまり「風邪とインフルエンザのシーズン」と具体的に言ってみてもいいのかもしれません。
This year’s cold and flu season may be longer than usual.
(今年の風邪とインフルエンザのシーズンは、いつもよりも長いかもしれません。)
So make sure you get a flu shot.
(だから、ちゃんとインフルエンザの予防接種を受けてくださいね。「a flu shot」というのは、インフルエンザの予防接種のことですね。)
ちなみに、インフルエンザは influenza と言うこともありますが、一般的には flu の方が広く使われています。
今問題になっている「鳥インフルエンザ」も、アメリカでは bird flu と言います。
そうそう、ちょうど今朝の新聞に、こんなにかわいい4コマ漫画が載っていました。スヌーピーやチャーリー・ブラウンの仲間たちが出てくる「Peanuts」シリーズです。
作者のチャールズ・シュルツ氏は、すでに8年前にお亡くなりになっていますが、今でも毎日、彼の昔の作品が新聞に登場しています。きっと、よほど人気が高いのでしょうね。
(Printed in San Jose Mercury News on 10/7/’08, originally published on 10/10/’61)
ルーシー: 「よしっ、今よ、咳をしてみて!」
(All right, now cough !)
ライナス: 「ゴホッ、ゴホッ、ゴホッ!」
(Cough ! Cough ! Cough !)
ルーシー: ドンドンと地べたを踏み鳴らす
(Stomp ! Stomp ! Stomp ! Stomp !)
ルーシー: 「もう二度と誰も苦しめられない風邪のバイキンの群れがここにいるわ!」
(There’s a batch of cold germs that will never bother anyone again !)
ルーシーちゃんは、風邪のバイキン(cold germs)は踏んづけると死ぬと思っているので、風邪をひいたライナスくんに咳をしてもらったんですね。そこをドシドシと踏んづけて、バイキンの群れをすっかりやっつけてしまったぞと、大満足。
この cold germs の germs というのは、「バイキン」という意味ですが、まだ子供のルーシーちゃんには、風邪のウイルスなんていう専門的なことはわからないので、「バイキンくん」になっちゃうんですね。
なんでも、ウイルスが発見されたのは1899年の事だったそうですから、それまでは、子供でなくとも、ルーシーちゃんと同じノリだったんでしょうね!
前回の「Did you mean ~?(もしかして、~ってこと?)」というお話では、アメリカ人のスペルのいい加減さに焦点をあててみました。
どうやら、彼らは耳から入った音をそのまま書いてみようとするために、ミススペルの嵐が起こっているのではないか? という仮説を立ててみたのでした。
このスペルのまずさは、個人的なメールやネット上の書き込みなど、私事の段階では納まりません。公共の場でも、堂々と横行しているのです。
たとえば、日々の生活には欠かせないフリーウェイの看板。
場所は、サンフランシスコとシリコンバレーを結ぶ幹線道路のひとつ、フリーウェイ101号線(US Route 101)。
101号線は、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州と西海岸の南北を結ぶ長い国道です。
サンフランシスコ・ベイエリアでは、Bayshore Freeway(シリコンバレーの辺り)や James Lick Freeway (サンフランシスコ市内)というニックネームでも親しまれています。
そんな幹線道路101号線には、次から次へと入り口や出口が出てくるのですが、その中に「Hillsdale(ヒルズデイル)」という名の出口があります。
残念ながら証拠写真はないのですが、そのヒルズデイルの看板が「Hillsidale(ヒルジデイル)」となっていたそうなのです。
う~ん、何を勘違いしたのでしょうか? きっと、この看板を書いた人には、ヒルズデイルの「ズ」という小さな音が、とっても大事な強調すべきものに思えたのでしょうね。
このヒルズデイルという出口は、シリコンバレーからサンフランシスコに向かって北上すると、ソフトウェア会社のオラクル(Oracle)のあるレッドウッドシティー(Redwood City)の次に出てくるものですが、この出口を下りて右(東)に行くと、フォスターシティー(Foster City)という静かな湾沿いの住宅街に出ます。
(こちらの航空写真では、左下の部分(北側)がフォスターシティーになります。真ん中の海は、サンフランシスコ湾です。)
この辺りは美しく整備された住宅街で、内海のサンフランシスコ湾や内陸部まで入り組んだ川には家々やアパートが面し、裏庭にはボートが停泊する家もある緑豊かな街並みとなっています。
(こちらの写真では、蛇行した川の右(北側)がフォスターシティーです。上部に左右に走っているのが、フリーウェイ101号線です。)
このように住宅街であるがゆえに、間違ったヒルズデイルの看板を見ながら、毎日通勤していた人もたくさんいるのでしょう。「いつもこの看板を見ていると、気持ちが悪くってしょうがない」という新聞の投書を読んだことがあります。
実は、このクレームは一年以上前に出されていたものなのですが、果たして、スペルミスはもう改善されているのでしょうか?
近頃、101号線のこの辺りを通ることはないので、いまだに確認はできてはいませんが、次回通るときには、チェックしてみることにいたしましょう。
けれども、間違いに気が付いていたとしても、この手のフリーウェイの看板は、架け替えるのが大変なんだそうです。なにせ、お金がかかりますからね。
フリーウェイを運転していると、出口の看板なんてそんなに大きくは見えませんが、実際には縦2.3メートル、横6.7メートルほどもあり、ひとつ作るのに5000ドル(約53万円)もかかるそうなのです。その看板代に設置する労働費を足すと、一枚架け替えるにしても、決してバカにはならないのです。
今は、上から下への財政難ですから、「ちょっとくらいのミスは大目に見てよ~」というのが、行政側の正直な気持ちでしょう。
(注:現在は、「ヒルズデイル」はちゃんとしたスペルになっております!)
ちなみに、話はちょっと逸れてしまいますが、現在、オラクルの高層ビル群がそびえ立つ場所は、昔は「マリーン・ワールド(Marine World)」という遊園地があったところです。水族館と動物園が合体したようなおもしろいコンセプトの遊園地で、サンフランシスコ湾沿いの広々とした敷地には、ボート遊びができる池や、動物たちが放し飼いになっている柵があったりして、のんびりと一日を過ごせる場所でした。
けれども、だんだんとこの辺の土地の価格が高騰して、税金を払うのが辛くなってきたのでしょう。1986年には、サンフランシスコのちょっと北にあるヴァレホ(Vallejo)という街に新しく遊園地を造って、こちらに引っ越しました。今でも、「ディスカバリー・キングダム(Six Flags Discovery Kingdom)」という名で営業を続けています。
(こちらの写真では、真ん中に池を囲んで建つビル群がオラクルの本社です。)
さて、話はガラッと変わりますが、前回の「Did you mean ~?」では、euphemismつまり「遠回しな言い方」というお話もいたしました。
たとえば、人種的な表現をぼかしてみたり、身体的に障害があることを間接的な表現に言い換えてみたりと、そんな例を出してみました。
それに加えて、こんなものもあるのです。そう、「お下品な表現」を避けて、ちょっと言葉を選んでみること。
たとえば、アメリカで頻繁に耳にする表現に、a pain in the butt というのがあります。
これを a pain in the rear end と、わざわざ言い換える人がいるのです。
この a pain in the butt という慣用句は、「イライラしてしまうような、うっとうしい人(物、出来事)」といった意味なのですが、最後の butt というのは、「尻」という意味ですね。つまり、日本語で言うと「尻が痛い」。
だから、直接的に「尻」と言うのを避けて、a pain in the rear end と言い換える人もいるのですね。
この rear end 自体も「お尻」には変わりはないのですが、butt よりも柔らかい、お上品な言葉なのです。どちらかというと、女性が好んで使う言葉でしょうか。
そう、わたしが初めて a pain in the rear end という表現を聞いた相手は、女性の弁護士でした。
ちなみに、お尻は buttocks とも言いますが、ここから butt という省略形が生まれたようです。
この buttocks は、あくまでも「臀部(でんぶ)」という意味であり、別に俗語でもないので、トレーニングのときに使ったりもします。
たとえば Squeeze your buttocks ! (お尻をキュッと締めて!)みたいに。
(ちなみに、こちらの写真は、なつかしいソニーのアイボーですね。3年前にサンノゼで開かれたロボットの祭典 RoboNexus に出展されていたものです。)
この a pain in the butt(もしくは the rear end)に類似した言葉に、a pain in the neck というのもあります。
やはり、こちらも同じような意味で、「うっとうしいような、退屈なもの(人)」といった表現となります。お尻の代わりに、「首が痛い」という言い方になるのですね。
なんでも、pain(痛み)という言葉を人に対して使うようになったのは、19世紀末のアメリカなんだそうです。「あんたを見てるとイライラするよ」というのを You give me a pain とか You’re a real pain と表現したのが最初なんだとか。
そこから a pain in the neck だの、a pain in the rear end だのと変形し、後にアメリカからイギリスへと派生していったということです。
(参考ウェブサイト:www.phrases.org.uk)
そうそう、a pain in the butt よりも、もっと「お下品な」表現がありましたよ。
それは、a pain in the ass 。
こちらの ass は俗語で、「尻、ケツ」という意味なので、いよいよもって、わたしがお話しした女性弁護士なんかは使いませんよね。
この俗語 ass を使った表現で、「ケツにキスをする」というのがあるのですが、これは「相手にこびへつらう、相手の機嫌をとる」といった意味になります。
相手のお尻にキスをするのですから、これはもう、最高の機嫌とりですよね!
おっと、ちょっと話が逸れてしまいましたが、「遠回しな言い方」 euphemism。
探してみると、他にもいろいろとありそうです。
追記: ついでに、「お尻」という表現をいくつか並べておきましょうか。文中でご紹介した butt、rear end、buttocks、ass 以外にも、bottom、backside、behind、rear、bum、buns、tush、tushy、can などといろいろあるのです。もちろん、この他にもたくさんあるようですが、これほど「遠回しな言い方」が存在する単語も珍しいかもしれませんね。
そうそう、一度、ホテルでマッサージをしてもらったとき、「このマッサージ台の上にお尻をのっけて」と言われて、とっさに何のことかわからなかったことがありました。このときは、tush (トゥッシュと発音)という表現が使われたのですが、こちらは何のことかとポカン。そこで相手は、bottom と言い換えてくれたのですが、とにかく、「お尻」は難しいものです。
何がって、アメリカに住んでいると、だんだんと単語のスペルがあやふやになってくるんです。
以前はちゃんとわかっていたのに、いつの間にか「i」と「e」の順番がわからなくなったり、「s」と「z」のどちらを使うのかわからなくなったりと、自分でも情けなくなってしまうくらいです。
この前も、「びっくりしちゃったのよ」とメールに書きたくて、I was surprised なのか、I was surprized なのか、迷ってしまったことがありました(もちろん、「s」を使った「surprised」の方が正しいものですね)。
それから、グーグルで英語の単語を検索していても、画面のトップにこう出てくることがあるんです。
Did you mean 〜 ?(もしかして、こっちの単語のこと?)
先日は、この単語でやられましたよ。 「euphemism」
この euphemism という言葉は、「婉曲(えんきょく)語」、つまり、「遠回しな言い方」という意味ですが、はっきり言及するとあまり好ましくないので、わざと遠回しに表現することですね。
この単語の発音は、「ユーファミズム」にも「ユーフォミズム」にも聞こえるので、わたしはてっきり「o」を使った「euphomism」かと思ってしまいました。
すると、グーグルさんからは、
Did you mean euphemism? と、すかさず返ってきました。情けない・・・
ご参考までに、この euphemism の例としては、たとえば、「黒人、black people」という言葉を避け、「アフリカ系アメリカ人、African American」という表現を使うことが挙げられるでしょうか。まあ、生物学的に言うと、人種の分類は Black で正しいのですが、社会的には、肌の色がどうのこうのと言うのは好ましくないということで、婉曲語である African American を使うようになったわけですね。
他には、「ハンディキャップのある、handicapped」という言葉を避け、「身体的にチャレンジのある、physically challenged」といったややこしい表現を使うことなどもあります。
ここだけの話ですが、アメリカ人ってスペルがあやふやなことで有名なんですよね。それは多分、耳から入った音をそのまま綴(つづ)ってみようとするからなんでしょうけれど、こっちまでスペルがわからなくなるなんて、「フフッ、わたしってアメリカ人みたい?」とちょっと嬉しいやら、「昔はちゃんとわかっていたのに・・・」と情けないやらで、複雑な気持ちになってしまいます。
アメリカ人にかかると、ほんとにスペルのいい加減なこと。「そんな面倒くさいことよりも、言いたいことを早く書きたいのよ!」と言わんばかり。
メールやパソコンで書いた文書なんかだと、まだ「スペルチェック」の機能があるからいいけれど、オークションサイトが流行り始めた頃なんかは、「自分で売りに出すものくらい、ちゃんとスペルをチェックしたら?」といったコメントがよく聞こえていましたね。
手持ちのアクセサリーを売りに出すときなんかは、もう大変。真珠を売りに出したいのに、「pearl」でなく「perl」と書いたり、ダイヤモンドのつもりが「diamond」でなく「dimond」となったり。
おしゃれなシャンデリア・イヤリング(凝った彫金のボリュームのあるイヤリング)なんて、きっと誰も正しくは書けないでしょうね。
だって、シャンデリアは「chandelier」と書くんですものね!(かく言うわたしも、ちゃんと辞書で調べました。)
こんなすごいのもあるんですよ。
アメリカで人気のサラダに Caesar salad (シーザー・サラダ)というのがありますよね。レタスにクルトンをのっけて、こってりとしたクリーミーなドレッシングで和えてあるサラダ。上にパルメザンチーズやグリルしたチキンものっかったりして、アメリカの料理にしては、なかなかおいしいものなのです。
ところが、あるピザ屋さんのメニューにこんなものが出現。
Seizure salad!
いえね、seizure というのは、「(病気の)発作」とか「(財産の)差し押さえ」という意味なんですよ。発音は「シージャー」というのですが、いかに「シーザー」に似ているからって、「発作サラダ」とは!
それから、もっとすごいのもありました。
以前、「Self-conscious(自意識)」というお話で、「self 〜」という単語の特集をいたしましたが、その中に self-deprecating というのがありました。ちょっと難しい表現ですが、「自分を卑下する」とか「謙遜する」という意味でしたね。
この self-deprecating が、こともあろうに、self-defecating となっていたのです。
あの〜、大変言い難いのですが、defecate という動詞は、排便することなんです。
実は、これは、れっきとした新聞記事の間違いなのでした。あるミュージシャンがコンサートでいろんな体験談を語ってくれたんだけれど、それは決して威張るものではなく、謙遜した、好感の持てる物言いでしたと、非常にいい内容(になるはず)だったのです・・・
ちなみに、この二つの例は、9月29日放映のNBCの深夜コメディー番組 『ジェイ・レノー・ショー(The Tonight’s Show with Jay Leno)』 から引用させていただきました。この番組では、「ヘッドライン(Headlines)」と称するコーナーがあって、全米のおもしろい新聞記事やら、変てこな製品やレストランの珍メニューを紹介する場となっています。ここで紹介するものは全部、視聴者が投稿した本物なんです!
写真では、右がジェイ・レノーさん、左がコメディアン仲間でトークショー番組のホスト仲間でもあるエレン・ディジェネラスさんです。
もう、大人ですら(新聞記者ですら)こうなのですから、子供になると、もっとスペルはあやふやになってしまいますよね。
新聞に毎日掲載されている4コマ漫画で、わたしがいつも楽しみにしている 『Secret Asian Man(神秘のアジア人)』 というのがあるのですが、先日、こんなおもしろいものを発見しました。
(by Tak Toyoshima、posted in San Jose Mercury News on 9/15/’08)
子供:「ママ、見てっ。僕、字を書いたんだよ!」
(Look, Mama. I wrote words !)
ママ:「これはすごいわ! サム、これを見てちょうだい!」
(This is awesome! Sam, take a look at this !)
そこで、パパであるサムは書かれた文字を見る。そこには、変てこな文字の羅列が・・・
パパ:「自分の名前をミススペルしているからって、会社を訴えることはできるのかな?」
(Can we sue companies for misspelling their own names?)
たしかに、アメリカでは、「Snak pak」だの「Quik Mart」だのと、わざと変なスペルにしてある店名や商品名が多いのは事実ですね(言うまでもなく、本来は Snack pack とか Quick Mart とすべきですね)。
まあ、そんなものを見ながら育っていると、そのうちに何が本物だかわからなくなってくることでしょう。
アメリカの金融危機:大恐慌以来の大ピンチ!
- 2008年09月30日
- 政治・経済
Vol.110
アメリカの金融危機:大恐慌以来の大ピンチ!
日本では、首相交代劇が繰り広げられる目まぐるしい9月ではありましたが、アメリカは今、蜂の巣をつついたような大騒ぎの渦中にあります。「住宅バブル」や「サブプライム問題」に端を発する金融界の粗相(そそう)が、国中を揺り動かす大問題に発展しているのです。
今月はまず、そんな金融業界のお話から始めましょう。
<金融ジェットコースター>
日本が「敬老の日」の3連休でホッと息をついている週末に、アメリカの金融業界では、休日返上でシビアな話し合いが続いておりました。ご存じの通り、証券老舗のリーマン・ブラザーズを誰が買い取るかという、あまり楽しくもない話し合いでした。
連邦準備理事会、財務省、大手金融機関のトップが一堂に会し、リーマンの行く末を協議するというのですから、そんなに楽しいわけがありません。
老舗のリーマンがバラバラにされて売られる? それ自体が狐につままれたような、「びっくり箱」でも手渡されたような話ではありますが、月曜日になってそのびっくり箱の蓋を開けてみて、もっとびっくり。買い手の有力候補となっていた商業銀行最大手のバンク・オブ・アメリカがリーマンを見捨てて、代わりにメリル・リンチを買収するというではありませんか。え、メリル・リンチも危なかったの?
そして、救いの手を得られなかったリーマンは、連邦倒産法第11章(通称チャプターイレヴン)の適用を申請し、あえなくその157年の歴史を閉じることになりました。
ウォールストリートの投資銀行の中では、今年3月に、業界5番手のベア・スターンズが大手銀行のJPモルガン・チェイスに買収され、今まさに4番手のリーマンが破綻、3番手のメリル・リンチが買収されようとしている。
次は、いよいよ2番手のモルガン・スタンレーと最大手のゴールドマン・サックスか?と、金融界には巨大なショックウェーブが巻き起こります。
経営危機は投資銀行に留まらず、この週には、保険会社としては世界的大企業であるAIGが米国政府から850億ドル(約9兆円)の公的資金を受けることになり、それに引き続き、消費者向け銀行のワシントン・ミューチュアルが買い手を探しているとも報じられました。
この予想もしない展開に、市場は騒然、「いったい何を信じたらいいの?」と業界通ですらパニック状態・・・(その後、預金高6位を誇るワシントン・ミューチュアルは、政府に差し押さえられ、JPモルガン・チェイスに売り払われています。)
金融破綻寸前ともいえるこの一週間は、まさに遊園地のジェットコースターも真っ青という株式市場の乱高下が見られたわけですが、一週間を終わってみると、何のことはない、ダウ平均株価は前の週の終値とほぼ同じ。1929年の大恐慌以来の、最大の金融危機と言われながら、ちゃんと市場が持ち直したのが唯一の救いとなりました。
しかし、胸をなでおろしたのもほんの束の間、翌週になると、さっそく連邦議会では政府が投入する7000億ドル(約74兆円)もの公的資金に関して議論が白熱し、市場はまたまた混乱へと逆戻り・・・
ふん、言い出しっぺの財務長官ポールソンとやらは、以前ゴールドマン・サックスのCEO(最高経営責任者)だった人間じゃないの。そんな悪者の仲間みたいな奴に7000億ドルもの小切手をハイッと手渡すわけ? そんなの血税を払う庶民としては絶対に許せない、ブー、ブー、ブー。
まあ、公的資金の議論はさて置いて、3月に買収されたベア・スターンズ、破綻したリーマン・ブラザーズ、そして急に買収が決まったメリル・リンチと3社の名を耳にすると、個人的にはそれなりに思い入れがあるのです。
まず、ベア・スターンズ。我が家では、ファイナンシャルアドバイザーの勧めもあって、マネーマネージャー(個人投資家向けの資産運用スペシャリスト)としてベア・スターンズを利用していたことがあるのです。が、成績はあまり芳しくなかったですね。それは市場が好調なときはいいのです。しかし、市場がこけると、自分もこける。これでは、専門家を雇う意味がないではありませんか。
幸か不幸か、昨年の夏、サブプライムローンの大問題が露見し、ベア・スターンズの息のかかったヘッジファンドがつぶれたのを潮に、ベア・スターンズとの関係は絶ってはおりましたが。
それから、メリル・リンチ。我が家は、ここに全財産を預けていたことがあるのですが、はっきり申し上げて、あまりいい場所ではありませんでした。
そして、リーマン・ブラザーズ。この方たちとは我が家は直接的な取引はありませんでしたが、個人的に思い出があるのです。
あれは、インターネット隆盛期でしょうか。まさに、世の中が「行け、行け」だった頃のこと。わたしの勤めていたシリコンバレーのスタートアップ会社が初めての製品を世に発表し、アメリカ市場と海外市場で同時に販売活動を展開し始めたとき、国内セールス担当者が最初に獲得した顧客の一社がリーマン・ブラザーズだったのです。
当時、リーマンといえば、ベンチャー企業にとっては、もう雲の上にいるような最上の顧客。なにせ、ウォールストリートの大御所様ですからね。お金はたっぷりあるし、彼らが顧客になってくれれば、それこそ絶大な宣伝価値がある。そんなネームバリューも手伝って、国内セールスの担当者は「リーマンが取れそう!」と、それはもう得意気でしたよ。
多分、リーマンの方も、これからネットを利用した新しいシステムを幅広く構築しようとしていたときでしょうから、どんなに小さなベンチャーが開発したものであろうと、便利な製品は採用してみたいと判断したのでしょう。
日本ではちょっと考え難いですけれど、もともとアメリカの金融業界には、「新し物好き」が多いのは確かなようです。
たとえば、手元に最新のメールを配信してくれることで大ヒットとなったリサーチ・イン・モーション社のブラックベリー(BlackBerry)端末は、ウォールストリートの金融関係者によって広まったようなものですね。スーツとネクタイという「コンサバ」な装いに反し、金融業界には、そんな新しい物にチャレンジする精神がみなぎっているのでしょう。
リーマン・ブラザーズにしたって、その成り立ちはチャレンジそのものだったようですね。1840年代にドイツ・バイエルン地方からアメリカに移住してきたリーマン3兄弟が南部アラバマ州に設立した小さな個人商店からスタートし、その後、南部では重要な換金作物だった綿花の取引で頭角を現し、南北戦争を機に、ニューヨークに進出して金融大手の仲間入りを果たす。
そう、南北戦争って、あの奴隷制廃止をめぐって起きた南部と北部の戦いのことです。そんな昔っから営業していたんですね(日本で言うと、徳川政権の終焉となる大政奉還の頃でしょうか)。
まあ、裏を返せば、金融業界のチャレンジ精神には悪しき部分がありまして、昨年の夏から世界を震撼させている「サブプライム問題」などは、このチャレンジ精神が災いしているわけですね。
だいたい、サブプライムローン(信用度の低い、おもに低所得層に貸し出される金利の高い住宅ローン)を買い集め、ひとかたまりにして、それを小さく切り刻んで有価証券として売り出すって、いったいどういうこと?
ニューヨーク・タイムズ紙のコラムニスト、トーマス・L・フリードマン氏は、このウォールストリート特有の「ギャンブル性」に関して、こんな風に書いていました。今回の大騒ぎが収まった暁には、次世代の数学の天才たちには、次から次へとこざかしい金融商品をエンジニアリング(開発)するのではなく、全世界に役立つエネルギーのテクノロジーをエンジニアリングして欲しいものだと。
まったくその通りかもしれません。近頃の気のきいた学生は、コツコツと研究を積み重ねていく地味な技術革新の分野や、資格を取るのが難しく責任の重い医療分野を避け、短期間で実入りが何倍にもなる金融業界を選ぶとも言われています。
一説によると、2006年の一年間でウォールストリートの大手投資銀行5社が支払ったボーナスは、実に360億ドル(現在の換算レートで約3兆8千万円)に上るそうですから、それは魅力を感じない方がおかしいのかもしれません。
そんな「濡れ手に粟(あわ)」的なマインドがこの金融危機を増長させた一因だったとしたら、それは、経済の仕組みの中で何かしらが根本的に間違っているということですね。
追記: リーマン・ブラザーズやメリル・リンチなどの金融大手5社は、日本では「証券会社」と報道されることもあるようですが、ここではアメリカの一般的な名称である「投資銀行(investment bank)」という表現を使いました。
投資銀行は、証券取引業務に加え、企業の株式市場公開を遂行したり、合併・買収のアドバイスをしたりと企業向けに総合的なサービスを提供するだけではなく、個人投資家にも門戸を開き、幅広い投資チャンスを提供しています。通常の銀行と違って、政府機関による監視が緩いので、投資銀行としては、もっともっと積極的な、悪く言うと「無茶な」運用を行える環境にあったわけですね。
なんでも、2004年には、大手投資銀行5社が結託して米証券取引委員会(通称SEC)に規制を緩めるように懇願し、それ以来、各社が保有する資産1ドルに対し、40ドルを借りても良いことになったんだとか。それまでは、資産1ドルに対し12ドルが限度だったそうなので、ずいぶんと緩くなったものです。もちろん借りたお金は、「投資、運用!」と、いろんなものの買いあさりに使われていたわけですね。
今回の金融危機のあおりで、残るふたつの大手投資銀行ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーは、自ら銀行となることを政府に申請し、これが認められています。今後、この2社のあり方は変わってくるでしょうし、これまで大手が行ってきた投資銀行業務には、小型の金融機関が参画することにもなるのでしょう。
<外交から経済へ>
降って湧いたような危機的な金融情勢に、メディアや国民の関心は一気にそちらの方に集中しているわけですが、今年はもうひとつ大事なイベントが控えていますね。そう、11月4日に迫る大統領選挙です。ふたりの候補者にとっては、もうあまり時間はないのです。
もちろん、金融危機が話題をさらっていることはあるのですが、もともとカリフォルニアでは、いまいち「ノリが悪い」感じがしています。なぜって、誰が候補であろうとカリフォルニアは最初から民主党支持と決まっていて、共和党がどうがんばっても、そちらに軍配が上がる事はあり得ないから。だから、両党の候補者が遊説することもないし、投票を懇願するテレビ・コマーシャルを観ることもありません。
そう、民主党のバラック・オバマ氏の陣営も共和党のジョン・マケイン氏の陣営も、カリフォルニアに行くくらいなら、オハイオ、ミシガン、ペンシルヴァニアの激戦州に勢力をつぎ込みましょうと思っているのです。
まあ、たまにカリフォルニアに足を伸ばすことはありますが、それはあくまでも、資金集めの「金蔓(かねづる)」として利用しているのですね(英語ではこういうのをcoffer、つまり「金庫」と言います。そう、カリフォルニアはでかい金庫なんです)。
一方、全米へと視野を広げてみると、ふたりの支持率は今のところ互角のようです。それは、オバマ氏の支持率が伸び悩みを見せる中、マケイン氏への支持率が上がってきていることに起因するようです。
ヒラリー・クリントン氏と民主党候補者の指名争いをしていたときには、あれほど輝いて見えたオバマ氏が、今は何となくくすんで見えてしまう。まさに、物を購入したあとに後悔する消費者のように「バイヤーズリモース(buyer’s remorse)」を感じている有権者もいるようです。
それに比べて、マケイン氏の方は、オバマ氏が正式に候補者指名を受けた8月末の民主党大会が終わった直後に、アラスカ州の女性知事サラ・ペイリン氏を副大統領候補とすると、まったく予想外の発表をしています。「なんと、保守的な共和党が女性を副大統領候補にしたぞ!」と、メディアや国民は度肝を抜かれたのと同時に、その斬新な決断に好感を抱く有権者も増えているようです。

マケイン氏は連邦議員を26年も務めたベテラン上院議員。かたやオバマ氏は上院議員一期目の若手ホープ。そんな国政レベルの実績の違いを笠に着て、マケイン氏は外交・国防問題の通であることを訴えます。
自分は海軍少佐として参戦したベトナム戦争では北軍の捕虜になった実戦経験もあるし、イラク戦争においても、派兵を増強すべしという自分の主張は正しかったのだ。「オバマくん、君は戦略と実戦の違いを何もわかってはいないんだよ」と、オバマ氏の対外的な経験のなさをグイグイと攻め立てます。
その一方で、マケイン氏は自らも認めるほどの経済音痴。経済政策に関しては、ブッシュ大統領に負けないほどの門外漢なのです。それに加えて、長い間お金持ちをやってきただけあって、庶民とはかけ離れた感覚を持っています(再婚した今の奥方は、ビール卸売りの大会社を相続したお金持ち)。
たとえば、いったい家を何軒持っているのかという質問に即座に答えられなかったり、金持ちの定義は何かと問われ「年収5百万ドル(約5億円)くらいかな?」と答えたりと、庶民にしてみればちょっと信じられないような感覚をお持ちのようです(一説によると、マケイン夫妻が所有する家の数は18軒なんだとか!)。
もしも何も起こらなかったのならば、マケイン氏がそのまま若干のリードを続けていたのかもしれません。しかし、起こってしまったんですね、金融危機が。
もちろん、これによって即座にオバマ氏が大逆転ということにはなりませんが、これから11月4日までのひと月間、国民の目は、ふたりの候補者が打ち出す「経済救済策」に注がれることになるでしょう。
今一番恐いのは、現状に恐れをなした金融機関の極度の「貸し渋り」によって経済全体が麻痺してしまうことです。実際に、銀行がお金を貸してくれないために、秋の収穫ができない農家や、日々の営業に支障が出るレストラン、そして住宅や車を買えない消費者と、全米で次々と実害が出てきているようです。
アメリカの貿易赤字は悪化の兆しを見せ、失業率は過去5年で最悪(6パーセント)となる中で起こった金融危機。「バブル」から「現実」へと変質した経済の混乱を、いち早く押し鎮める。これが次期大統領の最大の課題となってくるでしょう。
追記: 文中の写真は、第一回大統領候補討論会が行われた翌日、9月27日付けのサンノゼ・マーキュリー紙の一面です。この討論会は、「五分五分」もしくは「オバマ氏が僅差で勝ち」との評価が下されています。
大統領候補討論会はあと二回行われますが、たった一回きりの注目の副大統領候補討論会は、いよいよ10月2日に迫っています。
<おまけのお話:ペイリンさん、しっかりして!>

ちょっと余談になりますが、これだけは言わせてください。マケイン氏が副大統領候補に選んだアラスカ州知事のサラ・ペイリン氏は、個人的には悪い冗談にしか見えないのです。
実は、そう思っているのはわたしだけではなくて、マケイン氏がペイリン氏を指名した翌日には、サンノゼ・マーキュリー紙の一面に大きくこう書かれていました。「なんでサラ・ペイリン氏?(Why Sarah Palin?)」
そして、そんなペイリン氏は、近頃、恰好のパロディーの題材として引張りダコになっているのです。
たとえば、パロディー番組の王様『サタデーナイト・ライヴ(Saturday Night Live)』。以前レギュラーを務めていたティーナ・フェイさんがペイリン氏にえらく似ているということで、9月中旬のシーズンオープンには、さっそくペイリン氏役で古巣に舞い戻ってきました(フェイさんはもともとコメディーライターだったのですが、サタデーナイト・ライヴに出演するうちに人気が出て、今となっては映画の脚本も書くし、コメディアンとしてエミー賞も受賞するしと、大活躍のお方となっています)。

CBSのインタビュー番組を再現したスキット(9月27日放映)では、フェイさん扮するペイリン氏がこう発言します。
「わたしのいるアラスカからは、海を隔ててロシアが望めるの。だから、わたしはロシア外交には精通しているのよ。」
まあ、普通だったら、これは誰かが書いたジョークだと思うでしょう。けれども、何を隠そう、これは本物のペイリン氏が発言したことなのです。アラスカの片田舎の市長から州知事になり、知事として2年しか務めていない新米政治家に複雑な外交問題に対処することができるのかという質問に対し、ペイリン氏はこう答えたのです。
「実際にアラスカからはロシアが見えるわ(you can actually see Russia from land here in Alaska)。」
他にもこんな「名言」があります。副大統領候補に選ばれるちょっと前、イラク戦争について、これは神から授かった使命なのだと発言しています。「私たちの国のリーダーは、神から与えられた任務を遂行するために派兵しているのです(Our national leaders are sending them out on a task that is from God)」と。
かわいそうに、ペイリン氏にかかると、神様も「便利屋さん」に使われてしまうのですね。
けれども、どんなにパロディーのネタにされ、笑いの的になろうと、この恐ろしい事実は消え去ることはありません。もしもマケイン氏が大統領に選ばれ、任期中に彼の身に何かが起こったら、大統領に就任するのは他でもないペイリン氏なのです。(パロディー転じて、ホラー映画!)
夏来 潤(なつき じゅん)
ナパの一つ星レストラン
- 2008年09月15日
- Life in California, アメリカ編, 歴史・習慣
この「ライフinカリフォルニア」のセクションでは、前回「ナパの小さなワイナリー」と題して、ワインの名産地ナパバレーにある小さなワイナリーふたつをご紹介しておりました。
そのときのことをちょっと振り返ってみると、このナパの旅は、ごくきままな一泊旅行なのでした。どちらかと言うと、せっかく人気のホテルが取れたから、泊まりに行こうかしらといった感じでしょうか。
それでも、ナパまで足を伸ばすとなると、とても楽しみな旅路ではあります。連れ合いは、この日を待ち望んでいたようで、朝からいそいそとお弁当作りに励みます。
そうなんです。ちょっと変な話ですが、我が家ではどこかにドライブするというと、連れ合いがお弁当を作る習慣となっているのです。なぜって、お弁当を作るのが大好きだから。それに、朝は、女性はいろいろと準備に忙しいでしょ。だから、万年時差ぼけで朝の早い連れ合いが、シャキシャキッとお弁当を作ることになっているのです。
というわけで、無事にお弁当もできたし、11時ちょっと過ぎにエンジンをスタートします。
シリコンバレー南端の我が家からはドライブルートは結構複雑で、まず101号線をちょっと北上して680号線に移り、そこから780号線、80号線、37号線を経由して、ようやくナパバレーの目抜き通りとなる29号線にたどり着きます。
サンフランシスコ近郊にお住まいの方は、市内を経由し、観光名所のゴールデンゲート橋を渡って101号線を北上し、そこから37号線で東に折れナパ方面へと向かう、というのが常套手段だと思います。
けれども、サンノゼ市南部に住む我が家の場合は、サンフランシスコの対岸(バークレーとかオークランドのある所)の少し内陸部を北上し、直接ナパに出るようなルートとなります。いろいろと試したのですが、これが一番近道のようです。サンフランシスコ市内を通ると、途中、渋滞にひっかかることもありますしね。
幸いなことに、この日は独立記念日を目前に控えていたわりに、思ったよりも道が混んでいなかったので、最初の目的地であるピクニックエリアには、ほぼ2時間後に到着です。
そう、ナパやソノマのワイナリーには、ピクニックができるお庭のあるワイナリーがいくつかあって、そういうピクニックエリアでは、手弁当を食べたり、ワイナリーで購入したワインで舌鼓を打ったりできるのですね。
わたしたちが選んだのは、Vサトゥーイ(V. Sattui)というワイナリー。今では、日本の皆さんにもお馴染みになっていて、観光ツアーのルートにも入っていると聞きますが、ここのピクニックエリアは、ふかふかとした緑の芝生が広がる、とっても気持ちの良いお庭なのです。だから、我が家も、かなり前から愛用させてもらっています。
ワイナリーに付属するデリカテッセンでは、チーズやオリーブ、ハムやサラダと、ピクニックランチには最適の食材が手に入りますし、普段はあまり流通していない自家製ワインも買うことができます(近頃は、シリコンバレーのワイン小売店でもV. Sattuiのワインを見かけるようになりましたが、以前は、現地でなければ購入できませんでした)。
そんなVサトゥーイのピクニックエリアは、さすがに独立記念日を目の前にして、お客さんでいっぱい、ピクニックテーブルは満杯。だって独立記念日というと、みんなバーベキューやピクニックをするものと相場が決まっていますものね。
(ちなみに、こちらの写真の後方に写っている壁のようなものは、ナパバレー名物のワイン列車です。ゴトンゴトンと揺られながら、ランチを楽しめるようになっているのです。)
そんなわけで、テーブルはどこも満杯。けれども、心配はいりません。わたしたちは、折りたたみ式の椅子とテーブルという秘密兵器を持っているのです!
こんもりとした大木の陰に陣を敷き、さっそく連れ合いお手製の弁当を広げます。豚肉のケチャップソース炒めは、もうすっかり定番でしょうか。昨夜作ったマカロニサラダも、サラダ菜にくるまれてお出ましです。
そして、ワイナリーのデリカテッセンで買ってきたリースリング(Riesling)が、ランチのお供となります。なかなか味わい深い、フルーティーな白ワインなのです。
食前酒の働きもあるのでしょうが、屋外で食べるランチは、なぜだか食が進みます。おかずもおにぎりもパクパクと平らげてしまいました。
お腹が満たされてまわりを見回すと、ピニックエリアにはさすがに家族連れが目立ちます。目の前の芝生では、よちよち歩きの赤ちゃんを連れたお母さんを見かけました。
そして、木の根元に寄り添い、愛を語らう女性同士のカップルも。
直前の6月には、カリフォルニア州で同性の結婚が法的に許されることになりました。自分の州で同性結婚が禁止されていない限り、他州の人もカリフォルニアで結婚することが可能だそうで、遠い所からやって来たカップルもたくさんいることでしょう。
ワインの名産地ナパバレーというロマンティックな場所は、そんなカップルには最適なのかもしれませんね。
というわけで、そろそろチェックインできる時間となったことですし、食後にひと休みした後は、まっすぐにホテルへと向かいます。
ここはホテルというよりも、リゾートと呼んだ方がいいのかもしれません。広大な敷地の中にはコッテージ風の建物が点在していて、緑に囲まれた高台の部屋からは、遠くにナパバレーの盆地が望めます。
ここから眺めてみると、青々としたぶどう畑が盆地いっぱいに広がっているのが、手に取るようにわかります。まさに平和な、牧歌的な眺めなのです。
リゾートの名は、オーベルジュ・ドゥ・ソレイユ(Auberge du Soleil)。つまり、フランス語で太陽の宿屋ですね。
もともとは、1981年にレストランとしてスタートし、その4年後にホテルを建て増しして、宿泊客を受けるようになったそうです。それから20年以上、質の高いサービスで人気を保ってきました。決してお安い場所ではありませんが、その知名度のために、なかなか予約が取れないのです。
以前、フォトギャラリー「ワインの産地、ナパバレー」でご紹介したカリストーガ・ランチ(Calistoga Ranch)は、こちらのオーベルジュ・グループの系列リゾートとなります。
そんなオーベルジュ・ドゥ・ソレイユの部屋に案内してもらうと、シンプルで機能的なインテリアや行き届いたアメニティー、そして、木に囲まれた静かな環境にほっと息をつきます。連れ合いはピクニックランチのワインが効いてきたのか、さっそくふかふかのベッドでお昼寝です。
邪魔をしてはいけないとバルコニーに出たわたしは、近くの大木に集る小鳥たちを観察しながら、いつの間にか長椅子でまどろみます。この日はとても暑く、摂氏40度近くあったようですが、木陰のバルコニーはちょうどいいくらいの涼しさです。
お昼寝でリフレッシュした後は、いよいよレストランでお食事です。ここのレストランは、単に「オーベルジュ・ドゥ・ソレイユのレストラン(The Restaurant at Augerge du Soleil)」と呼ばれていて、ミシュランガイドのサインフランシスコ・ベイエリア版(2008年)では一つ星をいただいています。
お部屋からは、丘の斜面に作られた庭園をゆっくりと登り、あちらこちらに置かれた奇抜なオブジェやオリーブの木や草花を楽しみながらの到着となります。
この日は暑かったので、夕方6時半といえども、辺りはまだまだ暖かい空気に包まれています。というわけで、ディナーのお客様はみんな、ナパバレーのパノラマを望む、見晴らしのいいバルコニーに着席です。
ディナーはすべてコース料理になっていて、シェフご自慢のテイスティングメニュー2種類を選んでみたのですが、フレンチの伝統とシェフ独自の斬新さが相まって、お味もプレンゼンテーションもなかなかおもしろいものでした。
たとえば、こちらのお魚。前菜のひとつですが、白身の刺身に、なにやらベージュ色のプツプツしたものが添えてあります。ちょっとしょっぱくて「いくら」の一種かとも思っておりましたが、あとでその正体を聞いてびっくり。ゼラチン状のものに塩や生姜などで味付けしたものだそうです。きっと魚の卵みたいに丸くする道具があるのでしょうね。
刺身はもやしとわかめの上に盛られていて、かかっているソースは、日本風のお出しとなっています(英語では「Dashi」と書きますが、ダにアクセントのある「ダーシー」のように発音します)。
それから、こちらのリゾット。夏っぽく、エビとグリーンピースのリゾットに仕立ててありますが、お味は「ゆず風味のクリームソース(Yuzu cream sauce)」でした。ゆずの香りが、なんともすがすがしい清涼感を与えてくれます(Yuzu は、やはり最初のユにアクセントのある「ユーズー」みたいに発音します)。
ごていねいなことに、緑を添えるために、かいわれも入っていましたよ。
そして、こちらはかつおのたたき。かつおのたたき自体は、カリフォルニアのレストランではよく見かけるメニューではありますが、こちらには豚の角煮が添えてありました。
こってりしたソースのかかった香ばしい角煮が、お魚とおもしろい取り合わせとなっています。
このように、とくにお魚料理には「和」の影響が色濃く見られ、最後のお肉のメインディッシュよりもおいしく、印象深いものとなりました(もうそろそろお腹いっぱいというときに「ドン!」とお肉が出てきても、あまり食欲をそそられないですものね)。
とは言うものの、デザートは「別腹」。こちらのアイスクリームは、香辛料のタラゴン(tarragon、日本語ではエストラゴンというのが一般的でしょうか)の風味となっています。
添えてある揚げ物は、ギリシャ伝来のフィロ(Filo)でチョコレートクリームを包んで揚げたものです(フィロは薄く延ばしたパイ生地のようなもので、揚げるとパリッとして口当たりがとてもいいです)。
チョコレートで皿に描いた模様が、画家モンドリアンの絵のようでもありますね。ところどころに、黄金色(こがねいろ)のオリーブオイルをたらしてあります。色を添える意味もあるのでしょうけれど、フィロの揚げ物につけてもおいしいのです。
メインのお食事を終え、ちょうどデザートが運ばれて来る時刻になると、ナパの盆地は沈みかけた夕日で輝きを放ちます。
きっとこれも、ディナーに添える大事な「見せ場」のひとつなのでしょう。
この日は、連れ合いの手弁当と、ナパの一つ星のレストランで舌鼓。比べようもないけれど、わたしにとってはどちらも満足のいくものでした。
追記: 前回掲載した「ナパの小さなワイナリー」では、ソース・ナパ(Source Napa)というワイナリー(の事務所)を訪ね、オーナーのひとりであるトム・ギャンブルさんにテイスティングを披露してもらったお話をいたしました。実は、このソース・ナパのワインを勧めてくれたのが、今回ご紹介したオーベルジュ・ドゥ・ソレイユのレストランなのでした。
「もし白のソーヴィニョン・ブランがお好きなら、お勧めのものがありますよ」と、ベテランの給仕係の女性が持ってきたのが、ソース・ナパの「Gamble Vineyard Sauvignon Blanc」。その味わい深いソーヴィニョン・ブランにほれ込み、翌日事務所に押しかけたのが、トムさんとの出会いとなりました。
そのトムさんはこうおっしゃっていました。「そういえば今日、オーベルジュ・ドゥ・ソレイユからソーヴィニョン・ブランの追加注文が来ていたな。きっとあなたたちが最後の一本を飲んだんでしょう」と。
あの一本があったから、そして、レストランの女性がわざわざネットで検索したソース・ナパの情報を手渡してくれたからこそ、この嬉しい出会いに結び付いたんですね。
東京散歩
- 2008年09月11日
- フォトギャラリー
おっとどっこい、このフォトギャラリーのセクションは、もう一年以上も更新しておりませんでしたね!
忙しさにかまけて、ついつい無精になっておりましたが、久方ぶりに再開してみましょう。
最後にフォトギャラリーを更新した昨年7月から今までは、まずトルコへ旅行し、その後、日本には3回ほど帰国しておりました。その他にも、カリフォルニアでそれなりにいろんな体験をして、写真をどっさり撮ってはおりますが、とりあえず今回は、夏の東京の写真を載せてみました。
毎回、東京に行くと「お散歩」と称して写真をパチパチ撮っているのですが、今まで、夏の表情を掲載したことはありませんでしたね。四季のはっきりしている日本では、春と違って光線がくっきりしていて、辺りには力強い濃い緑が満ちています。
そんな暑い時期、汗をかきながらお散歩するのも、なかなか乙なものではありますが、今年は残念ながら、雨が多かったように思います。お盆を過ぎて、とにかく東京は毎日雨だったような記憶があるのですが、わたしとしては、それがとっても心残りではありました。
もちろん、あんまり暑いのもイヤですけれど、夏に雨は「らしくない」気がしませんか?「わたしの夏を返して!」って言いたくなるような・・・
今度はいつ日本に行くかは未定ですが、またお散歩の写真を撮るのを楽しみにしています。だって、日本ほど風情のある国は、世の中そんなにないと思いますもの。
音
- 2008年09月11日
- エッセイ
早いもので、もう9月となりました。
8月には北京オリンピックも開催され、連日、日本人選手の活躍に国中が沸き立っていましたね。ラッキーなことに、ちょうどオリンピック開催期間中に日本に戻っていたので、今回ばかりは祖国でオリンピック観戦ができて、とてもいい思い出となりました。
そんな夏の旅は、お盆を直前に控えた火曜日に始まりました。あまりパッとしないお天気で、東京駅の改札口を出ると、雨もよいのどんよりとした夕刻でした。
きっとずっと東京に暮らしていると、「あ〜今日は涼しいねぇ」というお天気なのでしょう。けれども、わたしは何はともあれ、その湿気を含んだ重い空気に閉口しておりました。
そんなじっとりとした空気から逃げるように乗り込んだタクシーが、東京駅を離れ、皇居をとり巻く大通りを進むと、いきなり「音」が聞こえてきます。そう、日本の夏の風物詩ともいえる蝉の声です。
北カリフォルニアでは、蝉の声を聞くことはまずないので、久方ぶりの蝉の合唱になつかしさを感じます。それにしても、こんなに大きな音でしたっけ?
わたしは心の中で、「これってまさか録音じゃないよね。生ゼミだよね」などと、くだらない事を考えていました。それほど、密閉されたタクシーの中にも音がズンズンと響いてきたのです。
それから2日ほどは、ホテルの中で仕事をしたりと外に出る機会があまりなかったのですが、3日目の朝、とにかく蝉の声が聞きたくてお散歩に出かけました。ロビーで知り合いのホテルマンに出会ったので、これから蝉を聞きに出かけてきますと告げると、「もう、そこらじゅうでワシワシ鳴いてますよ」との力強いお返事でした。
なるほど、日本全国そこらじゅうで鳴いているのは確かでしょうが、一番効率がいいのは、きっとこんもりとした森のある所でしょう。ということで、ホテルから歩いて数分の距離にある有栖川宮記念公園に向かうことにしました。以前、「世界で一番の散歩道」というエッセイに登場した緑豊かな公園です。
さすがに大木が鬱蒼(うっそう)と繁っているだけあって、ここでは、もう耳を覆いたくなるくらいに蝉の大合唱が響き渡っています。木が高くて姿はまったく見えませんが、きっと一本の木に何匹もとまっているのでしょう。わたしがすぐ下を歩いているのに、「我関せず」とばかりに、どの蝉も鳴きやみません。
やや行くと、土の道になりました。舗装されていない道を見るのは久しぶりだし、しかも東京で土の道なんて!と感心していると、何やら道にポコポコと穴が開いています。どうやら、蝉が抜け出した穴のようです。そこらじゅうに開いているところを見ると、相当たくさんの蝉が地下に生活していたようです。
そういう抜け穴を見ていると、「長い間ご苦労さまでした」と声をかけたくなってきます。
結局、この公園では蝉の姿を見ることはなかったのですが、翌日、別のルートをお散歩しているときに見かけました。六本木ヒルズのビル群の真ん中を通る「けやき坂通り」でした。
けやき坂という名前が付いているところを見ると、ここの並木はけやきなのでしょう。あまり大きくはありませんが、元気に青々と繁っています。
そんな「けやき坂」を、テレビ朝日を左手に見ながらトントンと下っていると、ごく間近から蝉の声が聞こえてきます。
この響きからすると、かなり至近距離のようですが、ふと見上げると、あっ、いた!
逃げないうちにと急いで撮ったので、すっかりピンボケになってしまいましたが、こちらの写真の真ん中に写っているのが蝉のシルエットです。たったひとり木の枝にしがみついて元気に鳴いています。蝉にしては、かなり大きな方でしょうか。
まあ、たった一匹であろうと、とにかく蝉の姿が見えたので、自分のミッションを果たしたようにひと安心でした。
そしてわかったのですが、蝉の鳴き声にも個人差があるのですね!
代表的な鳴き方は、「ミーン、ミン、ミン、ミーン」というものだと思いますが、間の「ミン、ミン」には、2つの場合、3つの場合、それから、ごく稀に4つの場合があるようなのです。それが個人差なのか、そのときの気分によるのかはわかりませんが、耳を澄ましてみると、蝉にもいろいろと事情があるのがわかります。
「ふん、俺は他の奴よりも、もっとうまく鳴けるんだぞ!」という蝉が、中にはいるのかもしれませんね。ということは、蝉も鳴き方の練習をするのでしょうか?
夏の音が聞けたことが、ちょっと嬉しいものでした。
追記: 蝉ってスズムシのように羽をこすり合わせて鳴くんじゃないのですね。ふと見つけた科学論文を読んでみて、そんな基本的なことを「発見」してしまいました。そういえば、なんだか子供の頃、そういう風に習ったような気もします。大人になると、すっかり忘れていました。
そう、蝉は、背中にある振動膜(timbal)を震わせて音を作るんですね。この振動膜には4本の肋骨(ろっこつ)が付いていて、これを筋肉で1秒間に120回も振動させて音を生成するんだそうです。この振動膜は左右に付いていて交互に振るわせるものだから、振動も倍。それをほとんど空洞になっているお腹に響かせ、そうやって増幅された音は、腹部に付いた鼓膜(こまく、eardrum)を通して外界に放たれる。
なんでも、世の中で一番大きな音を出す昆虫は、オーストラリアの蝉(Cyclochila australasiae)だそうで、1メートルの距離で測定すると、100デシベルもの騒音だそうです。
そもそもどうして蝉が大きな声で鳴くかって、メスを誘うためだそうで、だから、鳴くのはオスの方。きっと、大きな声を出した方が勝ちなんでしょうね。
不思議なことに、鼓膜を通してあんなに大きな音を放つわりに、蝉自身は涼しい顔。それは、耳の機能は鼓膜とは離れた場所にあって、ごく細い管で鼓膜と繋がっているだけだからだそうです。ゆえに、自分自身は、至近距離の巨大な音にさらされても聴覚を失わなくて済む。いやはや、自然のメカニズムとは、よくできたものですね。
(参考文献: Henry C. Bennet-Clark, “How Cicadas Make Their Noise”, Scientific American , May 1998)
ちなみに、蝉は英語で cicada と言います。「シケイダ」と発音するようですが、西海岸の人には馴染みの薄い言葉かもしれません。東海岸では、7年に一回とか、13年に一回と周期的に大発生する場所があるので、東の方々にはお馴染みとなっていることでしょう。
夏の思い出:オリンピックなど
- 2008年08月31日
- 歴史・風土

8月中旬、北京オリンピックが始まってすぐに日本に戻り、オリンピックが終わると同時にアメリカに帰ってきました。まずは、そんなオリンピックのお話から始めましょう。
<オリンピックの思い出>
今回の日本の旅は、仕事とオリンピック観戦に明け暮れることになりました。海外に住んでいると、なかなか日本人選手の活躍を観ることができないので、オリンピックの祭典もいきおい他人事となりがちですが、今回は日本にいたのでさすがに違いました。しかも、開催地が北京なので、ほぼリアルタイムで観戦できます。
録画ではなく、リアルタイムの昼間の観戦は難しいだの、なんとなく北京オリンピックには興味が湧かないだのと、いろんな私見を耳にしておりましたが、日頃日本チームには縁遠いわたしに言わせれば、そんなことは贅沢なことだと感じるのです。(写真は、アメリカ選手団の出発したサンフランシスコ空港に掲げられた「がんばれ!」との垂れ幕です。)
オリンピックといえば、開催国の都合で競技種目を変更したり、参加国が自国の有利になるようにルールを変えたりと、各国の思惑がドロドロと絡んでくるわけですが、それでも中継画面に釘付けになってしまうのは、選手たち自身がそんなドロドロとしたものとは無関係であるからかもしれません。あの笑顔と涙は、懸命に努力した者にしか見せることはできないのです。
前回のアテネと比べてメダル獲得数がどうだったかはわかりませんが、日本代表チームの活躍は素晴らしかったですね。やはり、一番印象に残ったのは、競泳の北島康介選手でしょうか。皆に宣言していた通りに、100メートル平泳ぎは世界新記録で、200メートルは惜しくも五輪新で金メダルとなったわけですが、あれだけ豪語したものを実現するなんてことは、そうそうできるものではありません。
それから、日本のお家芸である体操。仕事の合間にチラチラと競技進行を観ているうえでは、まさか男子団体総合で銀メダルを、そして内村航平選手が個人総合で銀メダルを獲得できるとは思ってもいなかったので、結果がわかったときには、もう少し真剣に観ていればよかったと反省してしまいました。
それにしても、日本の女子選手の元気のいいこと! 日本女性は「大和なでしこ」などといわれながら、どうして柔道やレスリングがあれだけ強いのでしょう? なにせ日本女子の獲得したメダル12個のうち9個は、柔道かレスリングなんですからね。おっとりとしたイメージに反して、大和なでしことは、心優しく、力持ちのことなんでしょう。
そして、ソフトボールチーム。まさか連敗した強豪のアメリカを相手に勝てるとは思っていなかったので、上野由岐子選手が決勝トーナメントの3試合を投げ抜き、最後の最後でアメリカをしのいだときには、こちらも一緒になって涙を浮かべてしまいました。
勝った人も負けた人も、選手それぞれに視聴者が惹かれるドラマがあるわけですが、ここまで祖国の選手を一生懸命に応援するのはいったいなぜなのでしょうね。それは、もしかすると、祖国が平和で安定した国だからなのかもしれません。
この北京オリンピックで、男子レスリングの松永共広選手が惜しくも決勝で敗れた相手は、アメリカのヘンリー・セジュド選手という21歳の若手でした。セジュド選手は、自身はアメリカで生まれ国籍を持つものの、両親はメキシコから来た不法移民。いつも摘発されるのを恐れ、西南部の州を転々として育ちました。4歳のときから母の手ひとつで育てられた彼は、そんな自分の逆境に泣き言をいったことは一度もないといいます。そして、両親から受け継いだメキシコの血を誇りに思うけれど、自分はあくまでもアメリカ人であり、自分をここまで育んでくれたアメリカは世界で一番の国であるといいます。
なるほど、何年アメリカに住んでも祖国は祖国だと思う人と、セジュド選手のように新世界に紛(まご)うことなき忠誠を誓う人の違いは、ここにあるのでしょう。つまり、祖国が安定していて「いつでも戻れる」と思っている人と、自分には新世界以外に祖国などないと思っている人の違い。
ともすると、アメリカに来る移民は、祖国とアメリカ両国に忠誠心を持つといわれますが、それはまさにケースバイケースなのでしょう。セジュド選手のように、自分の血や伝統は必ずしも忠誠の源とはならない場合もあるわけです。

一方、わたし自身は両国に深い愛着を持っていますが、オリンピックともなるとまったく別です。ソフトボールの決勝のときなどは、相手のアメリカ人選手がアウトになるのが嬉しくてしょうがなかったです。
それにしても、あの「USA! USA!」コールがあれほど耳障りに感じるとは、自分でも意外なことではありました。(写真は、東京都内で見かけた、2016年オリンピックの東京招致を願う垂れ幕です。)
<クレタ島の思い出>
話はガラッと変わって、以前旅したギリシャのお話をいたしましょう。一昨年の旅ではあるのですが、近頃妙に気になっていることがあるのです。夏といえば青い海、そういった季節柄の連想のせいでしょうか。
2006年5月号でもご紹介しておりますが、このギリシャ旅行では、前回のオリンピックの開催地でもある首都アテネを訪ねたあと、エーゲ海に浮かぶミコノス、サントリーニ、クレタの島々へと足を伸ばしたのでした。けれども、最後のクレタ島には1日半しか滞在できなかったし、有名な観光地はどこも見学していないので、とりたてて書かず仕舞いとなっておりました。ところが、そのクレタのことが、近頃妙に頭に浮かんでくるのです。
クレタ島というのは、ミノア文明の発祥の地といわれていて、それこそエーゲ海の源ともなるような文明を生んだ地なのです。ミノア文明とは考古学的には「青銅器時代」に分類され、紀元前2700年から同1500年に栄えた古い文明です。ミノス王が后の生んだ牛頭人身の怪物ミノタウルスを閉じ込めていたとの伝説のあるクノッソス宮殿で有名ですが、数々の発掘物や人々を如実に描いたカラフルな壁画などで、当時の生活ぶりも比較的よく知られています。
そのミノア文明は、突然ともいえるほどに唐突にこの世から姿を消してしまっています。この急激な凋落を指し、古代ギリシャ人はミノアのことを「アトランティス」とも呼んでいました(ミノアとは後世に付けられた名で、ミノア人自身が何と名乗っていたのかは今もってわからないそうです)。
そんなミノア文明を生んだクレタ島でわたしが滞在したのは、島の東側にあるエロウンダ(Elounda)という街。日本の観光ガイドにはあまり載っていませんが、欧米人に喜ばれそうなリゾート地で、完成間もないモダンなホテルでは行き届いたおもてなしをしてくれました。島々を結ぶ高速船が発着する港や本土への飛行機が飛び立つ空港を備えるイラクリオンからは、1時間ちょっと東に離れています。

宿泊した施設や静かな環境は最高のものではありましたが、わたしは何となく落ち着かない気分で時を過ごしていました。ひとつに、目の前の島が気になるのです。
リゾートが面する海は静かな内海になっていて、少し先にぽっかりと小さな島が浮かんでいます。波が穏やかなので、泳いでも行けそうなくらいの距離に見えます。島には定期的にボートが出ていて、見学をしようと、家族連れのグループが何組も海を渡って行きます。あちらへ渡ると島の遺跡を探索し、何時間後かにまたボートでリゾートへと戻って来る、そんな気楽な航行なのです。
この小さな島はスピナロンガ(Spinalonga)と呼ばれ、ちょっと風変わりな経歴を持っています。15世紀中頃、この辺りがイタリアのヴェネチアに統治された時代に、エーゲ海の脅威ともなっていたオスマン朝トルコとやり合うためにここに堅固な要塞が築かれました。現在目にする遺跡は、この頃に築かれたもののようです。
ヴェネチアとトルコが鎬(しのぎ)を削る中、スピナロンガは最後の最後までヴェネチアの手中にありましたが、18世紀初め、二国間の交渉の末トルコの統治下に置かれます。その後、オスマン朝はだんだんと力を失っていくのですが、オスマンに縁のある者は、キリスト教徒たちの報復を恐れ、この島を安住の地としたようです。けれども、間もなく、この島すら追われることになる。

そして、20世紀に入ると、この島はハンセン病患者の隔離場所として使われるようになります。第二次世界大戦後まで隔離施設として利用され、ヨーロッパ最後のハンセン病療養施設となったのだそうです。ここは海に囲まれた小さな島。ちょうどハワイのモロカイ島(Molokai)が「隔離」に選ばれたのと同じような理由だったのでしょう。
モロカイでは毎日青い海を眺めては、暗鬱(あんうつ)な気持ちで過ごしていたという体験談を聞いたことがあります。きっとこのスピナロンガでも、同じ気持ちで過ごしていた人々がたくさんいることでしょう。手の届きそうな対岸には村人たちが楽しく暮らしている。けれども自分たちは決して村に渡ることを許されない。いつ出られるともわからない、閉じ込められた生活。しかし、万が一そこから出られたとしても、村人との間には目に見えない有刺鉄線のようなバリアがある。
今となっては誰もいない静かな島には、日中、観光客がのんびりと訪れるだけです。
このスピナロンガの歴史はクレタ島を去る頃に知ったのですが、風光明媚な景色を目にしてもずっと心が晴れなかったのは、この島の数奇な運命が意識下で影響していたのかもしれません。
けれども、どうやら、それだけではなかったようです。もっと大きな出来事がクレタ島全体を襲っていたのです。
先にミノア文明は唐突に消えてしまったと書きましたが、長年の学者たちの論争の末、最近になってその原因が解明されつつあります。それは、天変地異。火山の大爆発と、それに続く大津波。

クレタ島から120キロメートルほど北にはサントリーニ島がありますが、ここは有名な観光地であるわりに、今でも活火山の上に乗っかっていて、とても危ない場所なのです。このサントリーニ島では、紀元前1600年に「ミノア噴火(Minoan eruption)」と呼ばれる大噴火がありました(サントリーニの別名はセラ(Thera)というので、「セラの噴火(Thera eruption)」とも呼ばれています)。
この大噴火の際、クレタ島から派生しサントリーニに点在するミノア文明の集落は、急激に降り積もる降下軽石に一瞬のうちに埋め尽くされました。が、被害はそれだけでは収まりませんでした。噴火によって巨大な津波が起こり、30分後には遠く離れたクレタ島にも到達したといいます。そして、その45分後には二つ目の津波が、その30分後には三つ目の津波が押し寄せたともいわれます。
津波は幅およそ50キロメートル、高さは優に30メートルを超えていたと見られ、クレタ島北東の沿岸部は、壊滅的な被害を受けたと考えられています。津波で直接的に流されなくても、この災害で急激に力をそがれたミノス文明は、やがてペロポネソス半島のコリントから遠征してきたギリシャ人に滅ぼされたともいわれています。
そして、わたしが泊まったエロウンダは、クレタ島の北東部。ちょうど大津波が押し寄せて来たと思われる場所なのです。3600年の昔、この辺りに住んでいた人々は、びっくり仰天したことでしょう。
ある晴れた日、大きな爆発音とともに空はにわかに夜のように掻き曇る。海沿いの集落は丘の斜面に張り付くように広がっていて、「何事が起きたのか」と家々の窓から外を眺めると、見たこともないような巨大な水の壁がこちらに向かって迫り来るではないか! 逃げようとしても、とても間に合わないし、逃げ場などありません。だって、丘のてっぺんですら、津波にすっかり飲み込まれてしまったのですから。
そんな人々の驚愕と叫びが、エロウンダに泊まっている間中、意識下で聞こえていたのかもしれません。それは、耳から入り大脳で処理する類の情報ではなく、遠い時空を越えてじわりと人に伝達する分析不能な波長みたいなものでしょうか。
そう、どんなに時代が変わろうとも、「アトランティス」の顛末は、現代人ともしっかりと繋がっているのかもしれません。
追記: ミノア文明の衰退に関しては、ここでご紹介した火山噴火による津波説の他に、噴火による地震説もあるようです。いずれにしても、サントリーニ島の噴火が遠く離れたクレタ島に壊滅的な被害を与えたという説には、多くの学者(考古学、古代地質学、火山学の専門家)が同意しています。
それから、「アトランティス」とは、古代ギリシャの哲学者プラトンの記述に初めて登場する伝説の島ですが、プラトンがどの歴史的事実をもとにこれを書いたのかは諸説分かれるようです。なかでもミノア噴火は、有力な説のひとつとなっているようではあります。
<夏の思い出>

あの日は、朝から蝉の声が響く暑い日でした。何かしら大事な放送があるというので、近所の班長さんの家の中庭に集合すると、ちょうど正午にラジオ放送が始まりました。それまで聞いたこともない天皇の声を録音した放送でした。
けれども、ラジオは感度が悪くガーガーと雑音混じりだし、第一、天皇の言葉が難し過ぎて、すぐには理解できません。しかし、まわりの大人たちが声もなく泣き始めたところをみると、ようやくこれは4年近くも続いた大東亜戦争の終結を告げる詔勅であることがわかりました。
あの日は、昭和20年(1945年)8月15日。子供たちばかりではなく、大人たちの中にも、玉音放送の中身が飲み込めない者はたくさんおりました。
「伍長殿、戦争は終わりました。日本は負けたのです。」
「バカを言え!神国日本が鬼畜どもに負けるわけがないではないか!」
読み書きの不得手な伍長殿は、部下の兵卒が指摘する日本の敗戦が信じられず、なかなか武装を解こうとはしませんでした。
そして、日本のあちらこちらでは、さまざまな反応が起こりました。学徒動員で学業が中断され、お国のために兵器製造に従事していた学生は、これで監督官を務めていた軍国教師に「何を生意気な!歯をくいしばれ!」とボコボコに殴られることもなくなると胸をなでおろします。疎開先の地方都市が空襲に遭い、更に山間部への疎開を強いられた生徒は、もうこれで逃げ回る必要はなくなるし、大好きな両親の元へ帰れると、戦争に負けた悲しさよりも嬉しさの方を感じます。
その一方で、戦争に勝つことができなかった不甲斐なさを天皇に詫びようと、自決を選んだ人々もいます。皇居の前には、そういった人々がたくさん集っておりました。
毎年8月になると、そんな夏の思い出がよみがえってきます。もちろん、わたし自身が体験したわけではありません。ですから、思い出は不思議と夏に凝固しているのです。まだ寒さが残る3月10日の東京大空襲でもないし、3日後の大阪大空襲でもありません。いつも夏のシーンが頭に浮かんでくるのです。
それは、個の思い出ではなく、集団の思い出ともいえるもの。自身は未経験であったにしても、集団の中の個に深く刻まれている記憶。いかに色褪せ、細部を失った白黒のシーンであっても、絶対に忘れられない集団の実体験。
20年前に79歳で亡くなった作家・大岡昇平氏は、晩年このようにおっしゃっていました。8月には、6日の広島の原爆投下記念日、9日の長崎の原爆投下記念日、そして15日の敗戦記念日という3つの大事なターニングポイントがある。だから、こんな飽食の時代にあっても、せめてものこと、毎年8月6日から15日の間は自国の平和について考えなければならないと。
大岡氏は、戦争文学の代表作ともなった『野火(のび)』という小説の中で、主人公にこう述べさせています。「この田舎にも朝夕配られて来る新聞紙の報道は、私の最も欲しないこと、つまり戦争をさせようとしているらしい。現代の戦争を操る少数の紳士諸君は、それが利益なのだから別として、再び彼等に欺(だま)されたいらしい人達を私は理解出来ない。恐らく彼等は私が比島(注:フィリピン)の山中で遇ったような目に遇うほかはあるまい。その時彼等は思い知るであろう。戦争を知らない人間は、半分は子供である。」(『野火』第37章・狂人日記より)
戦争を知る方たちがだんだんと減り、「半分は子供」の大人たちが幅を利かせるこの世の中では、毎年8月になると、夏の思い出を思い起こす必要があるのです。先達の甚大なる犠牲を無駄にしないためにも。そして、明日へと平穏な生活を繋げるためにも。
夏来 潤(なつき じゅん)
わたしはアメリカで生まれたわけでも、ヨチヨチ歩きの頃に家族に連れられてやって来たわけでもないので、最初にアメリカに住み始めたときは、それこそ片言の英語しかしゃべれませんでした。
まず、耳に入ってくる言葉がなかなかわからない。アメリカ人なら小さい頃から聞き覚えのあるような基本的な単語も、わたしにとってはまったく新しい言葉です。
困ったことに、キリンやカバやサイみたいな誰もが日本語では知っているような単語が、まったくわからないのです。だって、giraffe、hippopotamus、rhinoceros なんて言っても、最初は怪獣のようにしか聞こえないではありませんか。
それに、文章となると、もう流れが速すぎて到底ついていけない。あの単語はどういう意味だっけと考えているうちに、あっけなく話題は次へと移り行く。
聞くほうはまだしも、話すほうともなると、もうたどたどしいったらないのです。一応、自分の言いたい文章を作り上げることはできても、それに時間がかかりすぎるのです。コミュニケーションはピンポン玉みたいにポンポンと右から左へとはずまなきゃいけないものだから、相手はじれてしまって、すぐに興味を失う。すると、こちらは言葉を発するのさえ遠慮がちになってしまう。
幸運にもバイリンガル(もしくはマルチリンガル)に生まれた方々は別として、わたしのような体験は、外国語を習う上では誰もが経験することなのかもしれません。けれども、その当事者となると、苦労もまたひとしおといったところでしょう。
言葉なんて一夜のうちに上手くなるわけではなくて、だんだんと知らないうちに上達するものなので、ついつい「なんでわたしはぜんぜん上手くならないの?」と、あせりを感じることもあるでしょう。そして、その上達のプロセスの中では、相手にちゃんと話が通じないとか、相手からバカにされたとか、そんなことで悔し涙を流すこともあるでしょう。
個人的には、外国語なんて、悔し涙の量に比例して上手くなるものではないかと思っているのです。もしまわりに英語なりスペイン語なりドイツ語なり外国語が上手い方がいらっしゃったら尋ねてみてください。「あなたは、悔し涙を流したことがありますか?」と。きっと悔し涙を流さなかった人など、ひとりもいないと思います。
わたしはもともと英語が好きだったので、新しい言葉を学ぶのは自分へのチャレンジとして楽しめたほうかもしれません。
たとえば、耳を慣らすために、毎日テレビドラマを欠かさずに観ていました。その頃アメリカでは、30分のコメディータッチのホームドラマがたくさん流行っていたので、そんなものを観ながら、現実の生活でも使えそうな表現を学んでいました。「Three’s Company」「Different Strokes」「Too Close for Comfort」そういった題名があったでしょうか。コメディーなら話もそんなに難しくはないし、背伸びしない普段の言葉を使っていますからね。
あまり役には立ちませんが、Your face will freeze like that というのがあったのを覚えています。「(そんな変な顔をしていると)そんな顔になっちゃうよ」という意味ですね。「凍る(freeze)」という動詞がそんな使い方をされるのかと、ちょっと意外に感じました。
それから、ニュースを聞いていてわからない単語があったら、全部紙に書き出して、あとから辞書で意味を調べたりもしていました。わたし自身は、無意味な単語の羅列を覚えるのが苦手で、何かしら文章の中に出てきた単語を脈絡(context)で覚えるのが得意だったので、ニュースから聞き取った単語を内容ごと学ぶというのは、非常に合ったやり方でした。
だから、わたしは今でも人にこう勧めています。四の五の言わずに、丸ごと文章で覚えましょうと。そして、その文章をリズミカルに発音して自分のものとすると、なおいいですよね。すると、会話で使える文章のレパートリーも自然と増えることでしょう。
そんな風に地道に始まった英語のお勉強でしたが、それから何年も難しい本を読んだり、文章を書いては訂正されたり批判されたりを繰り返していたので、読み書き自体にも、英語での論議のやり方にもだんだんと慣れていきました。そうなると相乗効果が生まれて、聞いたり話したりするのもだいぶ楽になるものですよね。
と、何とも世間話みたいになってしまいましたが、いよいよ表題の「connecting the dots」に移りましょう。
この表題は、今話題の「iPhone(アイフォーン)3G」で有名なアップルの最高経営責任者(chief executive officer)スティーヴ・ジョブス氏のスピーチからヒントを得ました。2005年6月、彼がシリコンバレーの名門スタンフォード大学の卒業式で行ったスピーチに出てきたものです。
もともと connecting the dots という表現は、仕事の場面などでもよく使われるものではありますが、「点と点を繋いでみて、初めて全体の意味がわかってくる」というような意味合いがあります。
ジョブス氏はスピーチの中でこんな話をしていました。
僕は大学に入ってすぐにドロップアウトしてしまったんだけれど、すっかり大学を辞める前に、ひとつ「calligraphy(カリグラフィー、西洋書道・ペン習字)」のクラスを取ってみたんだよ。僕のいたリード大学は全米でも最も充実したカリグラフィーのクラスを持っていて、キャンパスのポスターやら引き出しのラベルやら、全部が手書きの美しいカリグラフィーでできているような所だったんだ。
そのカリグラフィーのクラスでは、いろんな書体だとか、文字と文字のスペースの取り方だとか、書体の発展の歴史だとかいろんなことを学んだんだけれど、そこには科学が解析できないような微妙な芸術的なニュアンスがあって、つい夢中になってしまったね。今になって考えてみると、それがすごく役に立っていたんだよ。だって、10年後に僕たち(アップルを創設した相棒のスティーヴ・ウォズニアック氏とジョブス氏)がマッキントッシュというコンピュータを初めて作ったときに、画面に出てくる文字には美しい字体を使ってみようじゃないかって思いついたからなんだよ。
もし僕が大学をドロップアウトしてなくて、カリグラフィーのクラスを取っていなかったとしたら、コンピュータの活字なんて、今ほど美しいものにはなっていなかったと思うよ。(マイクロソフトの)ウィンドウズの載ったパソコンなんて、所詮は何でもマック(マッキントッシュの愛称で現在の商品名)の真似だから、きっとパソコンのほうだって、味気ない字体のオンパレードになっていたはずだよ。もちろん、未来に向かって点と点を繋ぐなんてことはできないさ。こういうのは、10年後に振り返ってみて初めてクリアにわかることだからね。
もう一度言うとね、未来に向かって点と点を結ぶことなんてできない。後ろを振り返ってみて初めてできることだから。だから、君たちも、今経験しているさまざまな点が君たちの将来ではちゃんと繋がるんだっていうことを信じなきゃいけないよ。そう、君たちは何かを信じてなきゃいけないんだ。直感、運命、人生、業(ごう、仏教用語で「宿命」)、何でもいいんだけどね。僕自身はこういったアプローチで裏切られたことは一度もないし、僕の人生はこれでずいぶんと良くなったよ。
(この話はスピーチの初めの方に出てくるものですが、内容はある程度意訳しています。)
そう、点と点を繋いでみて何かしら意味を感じ取るなんて、自分の後ろを振り返ってみて初めてできることなんですね。今は「何でこんなことやってるんだろう?」と思うようなことでも、後になって考えてみると、「そうかぁ、あのときのあれが今の役に立ってるんだぁ」と感心することも多々あるわけです。
冒頭で、ドラマやニュースに出てきた単語をていねいに調べるという、わたしの英語学習術をご紹介しましたが、それだって今のわたしには充分に役に立っていると思うのです。
実は、どこかに昔のお勉強の跡が残っているに違いないといろいろと家捜しをしてみたのですが、見つかりましたよ、紙切れの数々が。よくもまあ何年も大事にとってあったものですが、いろんなサイズの紙切れに書かれた単語や言い回しを見直してみると、やっぱり、今となっては、ほとんどすべてわかるのですね。
ふむふむ、piece of cake ね。もともとはケーキの一切れってことですが、It’s a piece of cake と言うと、「そんなの簡単なことじゃん!」って意味になりますね。
それから、beat around the bush というのもありました。藪(やぶ)のまわりを突っつくのが転じて、「直接言及を避け、わざとまわりくどく言う」といった意味ですね。
考えてみると、そうやってひとつひとつお勉強したからこそ、頭の中の語彙(ごい)が増えたことは事実ですよね。一度では意味なんか覚えられないものもあるけれど、少なくとも、前に調べたことがあるくらいはわかるでしょ。そして、そんな積み重ねで語彙が増えたからこそ、今ではスムーズに物も読めるし、書くこともできる。
それから、その頃は、後で自分が物を書くようになるとは夢にも思っていなかったわけですが、ひとつひとつ言葉を大事にする昔からの習慣は、今のわたしには大いに役に立っているわけですね。
そう、後ろを振り返ってみて初めて点と点が繋がる。
You can only connect the dots looking backwards.
だからこそ、今は点でしかないようなことも、自分の将来においてちゃんと繋がるんだと信じなきゃいけない。
So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.
追記: ご紹介したスティーヴ・ジョブス氏のスピーチについて、ほんのちょっとだけ書いたことがあります。こちらの最後に掲載されている「おまけのお話:iPhoneを出せるアップル」というものです。
ここでも書いていますが、彼のスピーチの全文和訳をできないのがほんとうに残念です。






















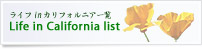
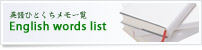
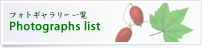

 Page Top
Page Top